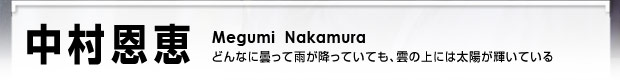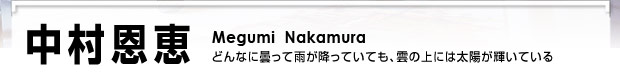長年活躍したネザーランド・ダンス・シアターから活動拠点を日本に移して3年、中村恩恵の舞台は、さらに多くの人を惹きつけている。
凛として、たおやか。そのたたずまいから静かだが強い熱情が放たれる舞台。
彼女の話はそんな舞台と同じように、誰をも魅了する力に満ちている。
Interview,Text : 林 愛子 Aiko Hayashi
Photo : 川島 浩之 Hiroyuki Kawashima
撮影協力 : BankART Studio NYK
この夏は中村さんが熊川哲也さんと踊った「Les Fleurs Noirs」、首藤康之さんと踊った「The Well-Tempered」を続けて拝見しました。皆さんものすごい集中力と緊迫感があっておもしろかった。
中村さんと踊ることで相手役のこれまでと違う魅力が引き出されていましたね。
あんなに練習したのに、しかも自分の振付なのに私、本番ですごく間違えるんです(笑)。
興に乗るとすっかり即興状態になってしまって、その時やりたいことがパッと出てきて、音も違うし手も違う。
パートナーはすごくびっくりして、それでたぶん普段出ない側面が出るのかもしれません(笑)。
それはダンサーが、中村さんの即興に応える力量を持ってないとできないことで。
熊川さんも楽しんでくださったみたいで。周りも認めるようなダンサーとしての長所が定着していて、普段使っている強みをあえて出さずに違う側面を出すというのはすごく勇気のいることですよね。
そこに観客はスリルを感じるわけですが、もちろん中村さんも舞台では相手によっても違うスリルを感じていらっしゃる?
そうですね、相手にもよるし作品にもよります。
たとえば首藤さんと違う作品を踊れば違うスリルがあるし、昨日と今日では違う発見がある。私のつくるデュエットは、はたから見ると簡単そうなんだけど、それがピチッとして見えるにはけっこう難しいらしくて。お互いにゆだねるところは相手にゆだねて、思い切りやるところはやって、自分だけ勢いでやったり固まっちゃったりすると失敗して次につながらなくなってしまう。
楽しいのはお互いに相手の機や動きの機を読んだりしながらダンサーとしての信頼関係ができていく作業なのですが。舞台でも、この人はこういう人なんだと初めてわかる瞬間があったりして、それもほんとに楽しいです。
中村さんがヨーロッパで踊るようになったのはローザンヌ・コンクールで受賞してすぐですね。
このコンクールはご自分で受けようと思ったんですか。
習っていた小倉礼子先生が、当時ご存命だった服部智恵子先生にお願いして特別クラスでみていただいた時に、大きくなったらローザンヌを受けなさいとおっしゃってくださったことが私の親の中にも残っていたようで。高校生になって大学進学するかどうか決める頃に、母が、コンクールみたいなものを受けてみれば相対的に自分がどんな場所にいるのか、外国では全然だめとかわかるんじゃない。また、その反対のこともあるかもしれないから、と。

相対的に自分を知るという、お母様のアドバイスは素晴らしいですね。バレエはどういうきかっけでいつから始めたのですか。
私たち家族がイタリアに住んでいた頃、天気予報みたいな番組のなかで予報の人の後ろで人が踊っていて、それを見た私が身体を動かしていたみたいで。
母もどういうものをやったらいいか考えていたらしく、日本に帰国してから県立音楽堂の知り合いの方に聞いたら、そこでいつも発表会をなさっていた小倉先生をご紹介いただいて、そのご縁で、5歳から始めて何十年、毎日毎日、同じことを繰り返して…(笑)。
イタリアへはどういうご関係でいらしたんですか。
父の仕事です。父はヴァイオリンをつくっていて、イタリアで最後の修行じゃないけど、仕事をして。みんなでついて行って1年半ぐらい住んでいました。
その時の記憶はおありですか?
よく覚えているのはアイスクリームのことで。すごくおいしいんですけど、私だけアイス食べるとおなかが痛いってなるから生クリームみたいなものしか食べられなかったんです(笑)。
中村恩恵
Megumi Nakamura

1988年ローザンヌ国際バレエコンクールにてプロフェッショナル賞受賞後、フランスのユースバレエ、アヴィニオンオペラ座、モンテカルロバレエ団等にて、バランシン、チューダー、リファール振付作品等のクラシック作品を踊る。
91-99年ネザーランドダンスシアター(NDT)に所属、イリ・キリアンをはじめ、マッツ・エック、オハッド・ナハリン、ナッチョ・ドゥアト等、現在の舞踊界をリードする振付家達たちと仕事をする。
99年NDT日本ツアーで 「One of a Kind 」の主導部を踊り、NDT退団後は、オランダを拠点に振付家、舞踊家として世界レベルの活動を継続。
00年自作自演のソロ作品「Dream Window」にて、オランダのGolden Theater Prizeを受賞。
01年キリアン振付のフルイブニングソロ「ブラックバード」を彩の国さいたま芸術劇場にて上演、この機にニムラ舞踊賞を受賞。
05年同劇場主催にて「A play of a play」を発表、好評を博す。またオランダで、コロゾープロダクションのプロデュースにて、自作自演ソロ作品「One 6」(1の6乗)を発表、ハーグのコルゾー劇場、ゼーベルト劇場、アムステルダムのベルビュー劇場で上演、好評を得る。
07年日本に活動の拠点を移し、横浜にDance Sangaを設立。Noism07の委嘱で「Waltz」を発表、舞踊批評家協会新人賞を受賞。
08年NBAバレエ団委嘱作品「露とくとく」、BankArt主催Cafe Live にて「夢みる権利」、大阪の野間バレエ団委嘱作品「Room」を発表。廣田あつ子とユニットを築き始める。
近年は、自らの舞踊活動の傍ら、キリアン作品のコーチとしてパリオペラ座をはじめ世界各地のバレエ団やバレエ学校の指導にあたり、06・07年度ローザンヌ国際コンクールのコンテンポラリーレパートリーのコーチをつとめる。

長年活躍したネザーランド・ダンス・シアターから活動拠点を日本に移して3年、中村恩恵の舞台は、さらに多くの人を惹きつけている。
凛として、たおやか。そのたたずまいから静かだが強い熱情が放たれる舞台。
彼女の話はそんな舞台と同じように、誰をも魅了する力に満ちている。
撮影協力 : BankART Studio NYK

今は外国に行くことはそんなに大変ではありませんが、中村さんの世代の方々は覚悟して身構えなきゃいけない場合もあったようで。でも中村さんからはそういう肩に力の入った大変さというのを感じないんですね、自然体で。向こうから舞い込んでくる話を、そのまま自分の仕事につなげていったという感じを受けますが。
そうでもないんです。なにかやりたいことがあると突然、積極的になるの。
普段は引っ込み思案なのに、これはすごくやりたいって思うと、そこに行って「あの私、ここに居たいんです」みたいな感じになって、けっこう押しが強いところがあって(笑)。
欧米のダンサーは、さあ私が舞台を支配するぞと意識的にアピールすることがありますね。
でも中村さんの舞台から受ける静かなる情熱というか、内から湧き上がってくる情熱はとても東洋的なものだと思います。
私はそれをオハッド・ナハリンに教えてもらいました。彼もイスラエル人なので東洋と近いですね。彼はギブ・インという言葉を使うんだけど、自分がとても小さいものであることを受け入れて、舞台に立っている時、自分からお客さんに向かって行くのではなく、向こうにいる人がこちらに引き寄せられてくるという見せ方がある、と。
もし自分の目が一度も見えた事がなく、こう踊ったらお客さんはどう思うかということを知らないで、ただ自分の内的感覚みたいなものを信じて踊ってみたらどんなだろうという感覚で動いてみて欲しいとか、ナハリンの指導でそういう地道な時間を費やしました。
クラシックはアン・ドゥオールで外に向かっていくものだから、それはとても新しい感覚、価値観で本当に勉強になりましたね。

アントニオ・チューダーのガラ・パフォーマンスのフレンチバレリーナ役をジャン・シャルル・ジルと。
フランスのユース・バレエでは古典を踊ることが多かったんですか。
いろんなものをやっていました。当時はちょうどフランス革命二百周年で、フランスの歴史とバレエの歴史をからめて、宮廷でバロックダンスを踊っている時に農民はどんな踊りを踊っていたかに始まって、ロマンティック・バレエ、フランスで衰退したバレエがロシアで発展して、ディアギレフのバレエ・リュスが来て、商業的なチャールストン、イサドラ・ダンカンの踊り、リファールの「白の組曲」などいろいろあって一番最後のほうにヌーベル・ダンス。それをもって一日3公演、何百回と踊って(笑)。
特にフランス国内の都市をバスで行くんです。昔は炭鉱で栄えていたけど今はさびれた山の中の町では劇場なんてないから小学校の校庭に板を張ったり。
青少年会館、古い劇場、映画館などどこでも踊りますが、一年に一回ぐらいしか行かないから子供達がずっと待ってて、次の日にバスで帰ろうとするとあとを追いかけてくる。
すごく可愛くていつも感動していました。
踊りながら舞踊の歴史を教えるなんて、貴重な経験ですね。
とても楽しくて勉強になって。ローザンヌで賞もらってすぐだったから団長さんは、恩恵はクラシック・ダンサーって思っていたみたいだけど、そこで同時代の振付家マチルド・モニエと仕事した時、ひどい筋肉痛になったんですがすごくおもしろくて、そのあたりからだんだん自分の興味がクラシック・バレエから違う方向へ行って。
ちょうど二十歳になる前、マッツ・エックのカンパニーの公演をカンヌで見た時に、衝撃的に感動してすごい踊りって思ったんです。でもそれは大人の世界、大人の表現で、自分がやるにはほど遠いって思っていたんですけれども。
ユース・バレエからカンヌの経験が、新しい作品を踊りたい、つくりたいという助走になったという感じでしょうか。
自分で選んで見たものではありませんが、前衛的な映画や音楽、踊りが好きな母にカニングハムのダンスなどに連れていかれました。
小倉先生も創作がお好きで、先生の娘さんがいつも子供のためにストーリーを書いてくださってそれに合わせて作品をつくったりしました。勧められて、よくバレエ・コンクールに自作自演で出ましたが、全然コンクール映えしないとんでもない作品になっちゃってましたね(笑)。
でもそこで、音楽や衣裳・照明を考えてつくるという楽しみを知ったと思います。
インタビュー、文
林 愛子
Aiko Hayashi
舞踊評論家 横浜市出身。早稲田大学卒業後、コピーライター、プランナーとして各種広告制作に関わる。そのかたわら大好きな劇場通いをし、’80年代から新聞、雑誌、舞踊専門誌、音楽専門誌などにインタビュー、解説、批評などを寄稿している。
フォトグラファー
川島浩之
Hiroyuki Kawashima
ステージフォトグラファー 東京都出身。海外旅行会社勤務の後、舞台写真の道を志す。(株)ビデオ、(株)エー・アイを経て現在フリー。学生時代に出会ったフラメンコに魅了され現在も追い続けている。写真展「FLAMENCO曽根崎心中~聖地に捧げる」(アエラに特集記事)他。

長年活躍したネザーランド・ダンス・シアターから活動拠点を日本に移して3年、中村恩恵の舞台は、さらに多くの人を惹きつけている。
凛として、たおやか。そのたたずまいから静かだが強い熱情が放たれる舞台。
彼女の話はそんな舞台と同じように、誰をも魅了する力に満ちている。
撮影協力 : BankART Studio NYK
お聞きしていると中村さんは、師との出会いに恵まれていらっしゃいますね。
自分にとって先生からいろいろ習うというのは、今やりたいというものに出会って心打たれ、意識して自分をかきたてて行動するわけでなく、自分のなかの思いがそうさせて、いつのまにか場が与えられているっていうんでしょうか。
それは大きなギフトだと思います。

NDT2でキリアンのステンピング・グラウンドを踊る。21歳のとき。
@LAURIE LEWIS
NDTでの経験を含めて中村さんのなかに強く残っていることは何ですか。
NDTはもともとお金のないところで、ダンサーが10人で自分たちの踊りたい演目のあるカンパニーを自分たちで作ろうとできたカンパニーでした。
キリアンさんがやり始めた時もとにかくポンとすぐに踊れるもの、バックセットも何もいらないもの、飛行機で着いて、衣裳に着替えたらすぐに公演が出来る様な作品が求められていました。
大事につくった一つの作品で再演を重ねて、次の創作活動の為の資金を作り出して行こうと必死でした。
私が渡欧したころはまだ,ヨーロッパが東と西に分裂している時代でした。キリアンさんもそうですが、東側の芸術家が表現の自由を求めて西側で活動をするためには、家族や祖国を捨てることになってしまう時代でした。私の同僚の中にも東側からツアー中に亡命して、そこで職を得て自分らしい踊りを追い求めてきたダンサー達もいました。頼る祖国も家族もない中で自分の芸でどうにか身を立てて生き抜いていこうというのが切実にあったと思う。
そういうところから作品をつくっていくのだということ、それがやっぱり私が海外で学んできたことといえるかもしれません。

キリアン作品は今、世界中のカンパニーがレパートリーに欲しがっているほどスタンダードになっている。中村さんはその作品の踊り手で指導者であり、ご自身が振付者でもありますが、今、ダンサーに望むことがあるとしたら何でしょうか。
体重が動いたらどうやって着くかを自分のなかでコントロールしたり、はずしたいと思ったらどういうふうにはずすか、自分の身体を知っていることは基礎ですが、特にパートナリングをする時に自分がどうやって立っているかをきちんと認識できない人は他者ともうまく対峙しあうことができないでしょう。
自分の踊りはこういう踊りでこういう美意識と価値観があってこういう立ち方です、と個人のなかで完結していても、そこに留まらずにそのことをきちんと相手とシェアしたり融通をきかせたり、寛容というのかな、相手を受け入れ相手を尊重する態度が必要だと思います。
でも、寛容なだけで自分の軸がない人とか、軸はしっかりあるんだけどガジガジで狭い人っていうのは、仕事がしにくくて限定したものしか与えられなくなってしまうので、それもすごく大事なことですね。
中村さんの踊りを見た方が、宇宙のなかの無重力を感じて、どうしたらそんなふうに踊れるのか、と。
引力のある地球に生きている私たちは、重力に縛られていますし、また同時に関節の可動域などの制約もあります。
その限定された条件のなかでも力学的なルールを上手に利用する事で自由に踊る事が出来るようになります。
また、想像力を使うことが大切です。例えば自分が上昇気流によって動かされていると思いながら動くのと、そう思わずに動いているのとは、異なる質の動き方をしている事に気がつくでしょう。異なる質の動き一つ一つをアナライズして、身体の細部にわたるまで意識に入れて日々のトレーニングを積み上げて行きます。

ヨーロッパと日本での舞踊の在り方の違いについてはどう思いますか。
日本に帰って来て3年ぐらいしかたっていないのであまり明確にはいえませんが、ヨーロッパの職業ダンサーは、カンパニーに属するか、小さな振り付け家主宰のグループに属するか、もしくはフリーランスとして活動をしていますが、、たとえばオランダでは、政府が決めた方向で助成金を出して、文化政策に反するとなかなか活動の場がないのが現状です。
だから自分たちがアートをやっていることが政府の方針に荷担しているみたいな、うまくいえないけど、社会の中でアーティストがこういう立場にあっていいんだろうかという立場におさまらないと次の作品発表ができない。たまたま自分の方針と政府の方針が合っていればいいけれども。
日本に帰ってみると、自腹を切ってスタジオを借りてやれば誰にも何も言われることなくやりたい作品が出せて、逆にアーティストにとって素晴らしい環境だと思うところもありますね。チケット収入を求めても、ヨーロッパはチケットが安いから死ぬほど踊らないとお金にならないし。日本だったらチケットもそれなりにお客さんが買ってみてくれて…。
一長一短ですが、必ずしも日本のほうが海外より恵まれないかっていうと、そうともいえない気がするんです。

長年活躍したネザーランド・ダンス・シアターから活動拠点を日本に移して3年、中村恩恵の舞台は、さらに多くの人を惹きつけている。
凛として、たおやか。そのたたずまいから静かだが強い熱情が放たれる舞台。
彼女の話はそんな舞台と同じように、誰をも魅了する力に満ちている。
撮影協力 : BankART Studio NYK

中村さんが落ち込んだことがおありかどうかわからないけど、怪我なさったりした時にはどうやって乗り越えたか、最後にお話いただけますか。
よくキリアンさんが言っていたのは、どんなに曇って雨が降っていても雲の上には太陽が出ているって(笑)。今大変でも、もうちょっと遠いところから見たり、もうちょっと遠いところを見れば、太陽はちゃんと輝いていてただ何かがさえぎっているだけ。
もしかして自分が怪我で踊れなくなってすごく悲しんだとしても、自分の人生全体でみれば、そのことがすごいプラスになっているかもしれない。だから与えられている状況が悪い状況っていうことはなくて、常にそこから何を学んでいくかで自分にとってプラスになるんじゃないか、と。
怪我ひとつとっても、それでもっと身体の使い方が工夫できたり、違う踊りの質みたいなものが見つかったり。私は腰が悪くてヘルニアみたいな感じなんですけど、オハッド・ナハリンも同じような病気をもっていて、彼からいろんな動きを教えてもらいました。
そういう病気がなかったら深く教えてもらえなかったかもしれないし、そうやって踊ることでいろいろ感知したり経験したり感動したことを含めて、自分の身体と向き合って何が無理で何が大丈夫なのか、必要かを沢山学べるし。
ぜひ怪我もひとつのギフトだと思ってきちんと向き合って、あきらめることはあきらめてやっていくのがいいと私は思うんです。
何かを一生懸命つかんでいると、次のものがつかめないでしょう?
必死でつかんでいるものを放したら、その手には次に何か違うものをつかむチャンスがあると思うんです。

絵描きの祖父がつくった木版

これまでこまごまと集めていたものが、ほとんどしまいこまれていてどこにあるかわからない。それでも自分が目につくものっていうのは、やっぱり見たいものなんだと思います。
私の父方の祖父が絵描きでエッチングをする人でした。この木版は、たぶんエッチングにする前のアイデアを描いたもので手に乗るほど小さいんです。
もう1つは、詩人のウィリアム・ブレイクの本で、私がオランダに行っていた頃、好きでブレイクの本を沢山集めていたら、それを知った私の父が、祖父が持っていた昔々のブレイクの本をくれました。これはヨブ記について描かれたものですが、イギリスの本なんて手に入りにくかった戦前、祖父はそういうものに影響されて創作をしたのではないかと思います。
私が生まれた時には祖父はもう亡くなっていて、祖父がブレイクの絵や詩が好きだったということを私は知りませんでした。でもどこか同じようなものに興味を持っていたことをあとで知って、伝達っていうのか、祖父の精神みたいなものが自分の血のなかに続いているんだな、と感じるんです。
戦争に行かないのなら戦争を推奨する絵を描かなければならなかった当時にあって、祖父は一切の絵をやめてしまいました。それで幼稚園をやって、そこの椅子などを沢山つくっていました。もしかしたら、祖父のような”絵は描かない絵描き”のことを聞いているから、自分のなかでも、踊るからダンサーっていうことがそんなに簡単ではあり得ないと思ってるふしがあるのかもしれません。
Q. 子供の頃に思い描いていた『夢』は何でしたか?
特に、何になりたいという具体的な思いはなかったように思います。私は、豊かな自然環境の中で育ちました。子供のころは、木々の新芽の優しい色や触感、野草の花々の可憐な姿や香り、夕立の稲妻にきらりと光る遠い山々の峰の広がり、そうしたものに心を奪われていたように思います。見ているものや触れているものに心が吸い込まれていくような時には、一瞬一瞬が完結していて時間が止まっている様な感じを覚えます。
未来には未知な領域が広がって行って、そこで出会うであろう物事がどのように自分に働きかけるかは全く予測できないように感じていたと思います。
Q. あなたのこれからの『夢』は何ですか?
スーフィーの詩人であるRumiの詩です。こんな舞に、人生の中で出会うことが出来たらと思います。
Dance, when you’re broken open.
Dance, if you’ve torn the bandage off.
Dance in the middle of the fighting.
Dance in your blood.
Dance, when you’re perfectly free.