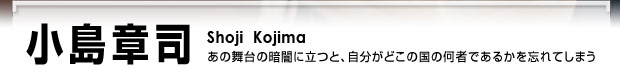日本におけるフラメンコのパイオニア、小島章司氏。
氏の少年時代、青年時代そして現在には、話題作を踊って舞台芸術の世界を牽引し、トップ・ランナーであり続ける小島氏のさりげなく鋭い美意識がにじみ出ている。
Interview,Text : 林 愛子 Aiko Hayashi
Photo : 川島 浩之 Hiroyuki Kawashima
先生は誰よりも早くスペインにいらしてますが、どのようなきっかけでフラメンコを踊るためにいらしたのですか。
そうですね、ひと言でお話するのは難しいんですけれども、人は生まれた時から人間と人間とのふれあいもあるし、どこか孤独で自分自身の心の中と社会との折り合いみたいなものをつけながら、孤独をちゃんと知って生きていくという、そういうことに小さい頃から目覚めていたのだと思います。
そして幸い、高校時代に素晴らしい先生に巡り会うことができて音楽大学を受験することになったんですが、田舎のことですからピアノを含めて音楽の勉強も高校の3年間だけで、武蔵野音大だけ受けたら入学することが叶いました。現在、芸術院会員であり、バリトン歌手でいらっしゃる畑中良輔先生が当時は声楽家を育てるカリスマ的な方で、すぐプライベートで教えを受けに行きました。蔵書の山の先生のレッスン場には慶応大学出身の若き日の若杉弘さんが伴奏にいらしていたりしていました。3日にあげず劇場通いをして、大きく世界観がひろがっていった時代でした。そんな中で音楽を勉強をしていた青年が、少しずつ文学や美術など他の芸術にも目覚めていったんです。
1961年は上野の東京文化会館のこけら落としでロイヤル・バレエのマーゴット・フォンティーン、リン・シーモアの踊りにふれることができました。ボリショイ・バレエの初来日ではレペシンスカヤの踊りを見てびっくり仰天。そういう時代にリアルタイムに生きて舞台芸術が何なのか、その厳しさと素晴らしさを感じて、劇場空間に対する大きな憧れが芽生えたんですね。初めて「フィガロの結婚」を畑中先生に薦められて私がフィガロ役で先生のスタジオで全曲歌わせていただきましたのもその頃です。
あれは1960年です、いくつかフラメンコのカンパニーが来日して、ピラール・ロペス舞踊団はピラールの相手役がアントニオ・ガデス。もう一つのアレグリアス舞踊団は全体がスペインのフォルクローレの紹介という感じでしたが、ピラールの場合はもっと劇場芸術としての優れた要素が内包されていたんです。そのあと何年かしてカルメン・アマヤの「バルセロナ物語」が上映され大きな衝撃を受け、1964年の東京オリンピックでは世界中の人が手をつないで、人間の絆や人の輪というものを感じたんです。で、僕もスペインに行こう、と。その時決心がついたんですね。
戦後の復興期50年代から60年代、人々があらゆるものを吸収する意欲は、今とは想像がつかないものだったといわれます。
今も、芸術家は自分の理想に向かって大きな犠牲を伴って生きていると思いますが、私の場合はちょっと特殊かもしれませんね。ほんとはオペラ歌手になれればいいと思っていたんです。初来日のイタリア・オペラで伝説のマリオ・デル・モナコの「オテロ」、レナータ・テバルディの「トスカ」、ジュリエッタ・シミオナートの「セビリアの理髪師」のロジーナ、そのような偉大な歌手たちの名演奏を聞いて、自分のやっていることに疑問を抱きはじめ、そして打ちのめされました。オペラ歌手になるということが、そこでベールに覆われてしまって、硬直してしまった自分がありましたね。

先生のお声はよく響いてほんとに心地よいです。
ところで、いろんな踊りがあったわけですけど、フラメンコを選ばれたのはどうしてでしょう。
言葉で表すのは難しいですけどフラメンコの、あの歌い手やギタリストの独特な音楽ですね。クラシック音楽のように短調も長調もありますが、そのはざまにある音楽、フラメンコでは”ミ”の旋法。長調でも短調でもない響き。自分が今までクラシックでベルカントやドイツ・リートのフィッシャー・ディスカウやエリザベート・シュワルツコップといった方たちの声にふれていたところにフラメンコのだみ声やひびわれたハスキーな地声を聞いて。日本の民謡よりももっとソバージュな、限りなく日常的であるものと限りなく非日常的で宗教的な儀式なんかにも含まれている、そういう二つの世界に属しているもの、そしてもちろんそのはざまにあるもの。それがたぶん私の心をかきむしったんじゃないかと思うんです。もちろん、踊り手の紡ぎ出す足音や手拍子なども強烈なインパクトを与えました。
フラメンコは人間の孤独を表現するのにとても適しています。恵まれた環境にいてさえも、人は生まれながらに孤独な存在であるという…。
先生ご自身もそういうことを感じる少年でいらした、ということで。
人は誰しも子供の頃は、スポンジが水を吸うように感受性がほんとに強い。存在そのものが感受性のような時代に日々を過ごしていくんだけど、やっぱりあんな小さな子供時代でも何か負の要素っていうか、黒いものを感じた時にそれはとてつもなく膨らみ、背負いきれないほどの十字架と思ってましたけどね。だんだん大きくなって、神様は一人の人間が背負いきれないほどの重い十字架を背負わせることはない、っておっしゃる方もいますけど。でもなんかこう、ふっと自分に何があるんだろうか、自分に何が必要なんだろうというようなことを考えるものなんですが、ある種の欠乏感と闘いながら成長してゆくものなのでは。
四国は瀬戸内海に面して、海洋系の精神風土というか、地中海に面したスペインとどこか似たところもあるようにも感じますが。
そうですね、私の生まれ育った家からは、歩いてすぐ海に出られました。子供の頃、部屋の窓を開けると、輝く月が冴え冴えと、とてつもなく大きく見えたことを覚えています。
小島章司
Shoji Kojima

| 1939(昭和14)年。徳島県生まれ。 武蔵野音楽大学声楽学科卒業。日本フラメンコ協会理事長。 |
|
| 1966年 | スペインに渡り、マドリードの稽古場「アモール・デ・ディオス」で修業。 |
| 1976年 | 十年に及ぶ修業を終えて帰国。 |
| 1986年 | 『瞋恚の炎』で第18回舞踊批評家協会賞、芸術祭賞を受賞。 |
| 1991年 | 河上鈴子スペイン舞踊賞を受賞。 |
| 1999年 | 徳島県文化賞を受賞。『ガルシア・ロルカへのオマージュ』で第30回舞踊批評家協会賞、平成11年度舞踊芸術賞を受賞。 |
| 2000年 | 『LUNA フラメンコの魂を求めて』で第50回芸術選奨文部大臣賞(舞踊部門)を受賞。 |
| 2000年 | 12月、スペイン国王よりイサベル女王勲章オフィシアル十字型章を受章。 |
| 2002年 | 『アトランティダ幻想』で第33回舞踊批評家協会賞を受賞。 |
| 2003年 | 紫綬褒章を受章。 |
| 2004年 | 韓日伝統文化交流協会より功労牌を授与される。 |
| 2005年 | スペイン・アンダルシア州政府より顕彰される。 |
| 2008年 | 『鳥の歌』『FEDERICO』『戦下の詩人たち』の〈愛と平和三部作〉により第39回舞踊批評家協会賞を受賞。 |
| 2009年 | 4月、スペイン国王より文民功労勲章エンコミエンダ章を受章。 |
| 2009年 | 6月14日、高野山真言宗総本山金剛峯寺壇上伽藍金堂にてフラメンコ奉納公演『聖なるいのち ~空海に捧ぐ~』を行う。 |
| 2009年 | 11月3日、文化功労者に選ばれる。 |
舞踊評論家 横浜市出身。早稲田大学卒業後、コピーライター、プランナーとして各種広告制作に関わる。そのかたわら大好きな劇場通いをし、’80年代から新聞、雑誌、舞踊専門誌、音楽専門誌などにインタビュー、解説、批評などを寄稿している。
ステージフォトグラファー 東京都出身。海外旅行会社勤務の後、舞台写真の道を志す。(株)ビデオ、(株)エー・アイを経て現在フリー。学生時代に出会ったフラメンコに魅了され現在も追い続けている。写真展「FLAMENCO曽根崎心中~聖地に捧げる」(アエラに特集記事)他。

日本におけるフラメンコのパイオニア、小島章司氏。
氏の少年時代、青年時代そして現在には、話題作を踊って舞台芸術の世界を牽引し、トップ・ランナーであり続ける小島氏のさりげなく鋭い美意識がにじみ出ている。
海外との行き来も楽な今と違って、やはりある種の覚悟っていうものをお持ちになっていらしたんですか。
はい、私の場合は声楽を10年、バレエは谷桃子先生と橘秋子先生のところで約7年間習いました。
スペインに行くことを決めた時にはいろいろと身辺整理をして、で、横浜から船に乗ってシベリア鉄道で。

ナホトカからずっとソビエトの横断。先生はもともと音楽のベースが広くていらしたから、ご苦労はなさらなかったのでは。
最初に習った先生がスペイン語で「ムイ・ビエン」と。
それはフランス語で「トレ・ビアン」の意味ですから、もうびっくりしちゃって。だったらスペインまでわざわざ勉強しに来ないよって思ったりして。
でも一般的にスペインの先生方は、先生のおっしゃることがだいたいできれば「いい」っておっしゃるんです。
日本の芸道物語はまた違いますよね、厳しくてちょっとしごきの世界みたいで。
大学時代、歌舞伎は6代目歌右衛門さん、今の幸四郎さんのお父様の白鴎さんや尾上松禄さん、梅幸さんの時代で、私は全盛期の歌右衛門さんのおっかけみたいによく観ました。高校生の頃には今の坂田藤十郎さんが中村扇雀の名でお父様の雁次郎さんと「曾根崎心中」で共演した舞台を初めて見て口あんぐりでした。
日本独自の舞台を体感していらした。
そこには役者さんが舞台に立った時の限りない静けさが、イタリア・オペラのピアニッシモとフォルティシモとはまた違う、独特の間(ま)がありますね。何もしなくても静けさから、観客にはぴりぴりと伝わるものがある。その静寂、静謐さみたいなものは、自分の中には備わっていたような気がします。フラメンコには地中海気質の騒ぎ過ぎるような要素もありますが、自身のうちなるもの、内に秘めたるものとのコントラストはとても大切なのではないかと思います。

戦争が終わって荒廃していたあの時代に、辛抱強さ、忍耐強さみたいなものはやっぱり人に負けないようなものが培われたような気がしますね。舞踊家にしてはもう26歳でしたから、遅すぎるくらいに思っていましたけど。まあ、自分が決心できた時がその時だ、と。
いつも悩んでいましたけど、桃栗3年柿8年という言葉がありますが、10年いれば最低のことは勉強できるかなと思って。
でもずいぶんラッキーで、次の年から結成されたばかりのスペイン国立舞踊団へ入団して、68年にはスペイン歌謡の大歌手ラファエル・ファリーナに見いだしていただいて、首都マドリッドの公演に1か月出させていただいたり。日本でいえば村田英雄さんや三波春夫さんみたいな方と思っていただければ。フラメンコも歌うしフォルクローレ的な歌も歌うという方でした。
そういうなかで、嫉妬に合ったりとか、いやな思いはなさらなかったですか。
契約もしてファリーナさんの舞台にいざ出ることになったら、他の人より私のほうが看板も大きくて。そこに群舞や歌い手がいて、歌い手の方がそんな異国の人間のために歌うのはいやだと言ったとかで、それなら私は歌なしで踊りますって言っちゃったんです(笑)。
どこか自信のないところもあるけど、いざとなったら毅然としているという、私にはそういう面があって。フラメンコのよさはよくわかっているけれど、子供の頃から日本の舞台に親しんできたから違った意味で私は、あなたたちにはない東洋の神秘性みたいなものをどこかに宿している、と確信して。だから、非難とか中傷に対してはそれほど苦しいとは思わなかったですね。
もちろん、そういうフェアじゃないことはそれとしてとらえて受けていくことはその時に覚えたし、そういうことを言う人のほうに逆にあわれみを感じたというか。
その後しばらくして国立テレビの番組で大きく取り上げていただき、その番組を通じて全国に出演する機会を得、アンダルシアで今でもフラメンコの老舗になっているロス・ガージョスなどのタブラオにいっぱい出させていただくチャンスがあって。その時、親身になってフラメンコの「はじめに歌(カンテ)ありき」みたいなことまで教えてくださった親切な人たちもいましたし、そういう意味ではいろんなことをあの10年間で学ばせていただきました。

日本におけるフラメンコのパイオニア、小島章司氏。
氏の少年時代、青年時代そして現在には、話題作を踊って舞台芸術の世界を牽引し、トップ・ランナーであり続ける小島氏のさりげなく鋭い美意識がにじみ出ている。
日本人としてのアイデンティティというものが明確におありだからこそ、先生が踊ると国境を忘れさせるんですね。
カナリア諸島のラスパルマスで踊っている時、小島章司をとおしてフラメンコのインターナショナリゼイションが始まるみたいなことを新聞が書いてくださったけれど、それは心と肉体と両方を通して、国境なんかありはしないということを表現したのだと思います。あの舞台の暗闇に立った時、自分がどこの国の何者であるかなんて忘れてしまいますものね。すべての国境なんてなくなればいいのではないか、特に舞台芸術においては。70歳を過ぎてからなおさらそれを感じています。

『カディスの女』 撮影:平地勲
あれは82年、先生の「カディスの女」を拝見させていただいた時は衝撃でした。フラメンコではマチスモといいますか、男性ダンサーはそこで男性らしさを見せますが、国境だけでなく男女を超えた先生の独自のスタイルはどのようにして生まれたのでしょうか。
10年間のスペイン滞在を終えて行なった帰国公演は、今では全員珠玉のメンバーで、相手役のメルチェ・エスメラルダもスペインを代表する舞踊手だし、カルメン・リナーレスも現在女性ナンバーワンのフラメンコ歌手で。そういう方たちと全国6カ所で公演して、またスペインに帰るつもりだったんですけど、日本に残って日本のフラメンコにも心を開いて教えてくださいという意味のことを言われました。
それで、80年にここの稽古場ができるまではスペインと日本を行き来しながら途中パリで教えたり、日本での教授活動が始まりました。
日本で初めて教えていたのは、ほとんど女性たちでした。それまでは僕も普通に踊っていましたが、そこでやっぱり女性の振り、腰の動きや肩の動きをどうしたらいいのかを考えるようになって。
当時は日本でフラメンコを歌う人たちもいなくて、あらゆる面で自分の納得するようなメンバーで舞台を創り上げていくことがまだ困難なようなイメージがありましたね。そのうちに「カディスの女」と題して、フラメンコのなかで一番ドラマチックなペテネーラの歌詞をいくつか組み合わせて物語を組み立てて創作することになりました。私の衣裳は稽古着で、フラメンコのショールをはおっているだけ。下は黒いパンツにいわゆるレオタード風な上着を着て面をつけたんです。
先生の踊りは、手の表情をはじめとしてニュアンスに富んで。ほんとにインパクトの強い作品でした。小島先生の存在があって、今、佐藤浩希さんたち男性ダンサーが活躍しているのはうれしいことです。男性ダンサーが増えないと活性化されませんから。
そうですよね、なんというか舞台のなかで一種の重厚さみたいなものが。やっぱり男性舞踊手は背も高いし、重みもあるし。そういう物理的なことだけではなくて舞台の上でのいろんな色合いも増します。


2009年には、高野山で踊られました。
踊りは神に捧げるものでもありますね。
踊る時は巫女ですね、舞い、踊り、祈り、そうして天と地をつなぐのものだと。
子供の頃、四国でしたのでチリンチリンと托鉢に来る僧侶や八十八カ所回っている巡礼者の方たちに米びつから米をすくってさしあげるとか、ふかしたさつまいもをさしあげるというお接待をしたり、近所の人たちに手を引かれて御経を唱えに観音様に参ったり。四国出身の空海が中国大陸へ渡って勉強して教典もいっぱい持って帰ってきた、という古来からの言い伝えも聞いていました。で、つい2、3年前にきっと僕の心に今あるものは、空海の影響ではないかと思い始めたんですね。そういう接待の心や、祈るということ。それは空海の存在があったから。その空海のために全霊をこめて踊りを捧げたいと決心して、高野山の本山にお願いにあがりました。
素晴らしい企画ですね。
初めてのことだったらしいんですが、自分の魂のために踊らせていただきたい、と。佐藤浩希さんたち男性舞踊手と11人の僧侶の方にも出演していただいて。代表格のお坊さんには声明に関してのことをいろいろ教わって、それで1時間の作品を踊らせていただいて。
奉納フラメンコですね(笑)。

日本におけるフラメンコのパイオニア、小島章司氏。
氏の少年時代、青年時代そして現在には、話題作を踊って舞台芸術の世界を牽引し、トップ・ランナーであり続ける小島氏のさりげなく鋭い美意識がにじみ出ている。

いろいろなところで後進の指導をなさっていますが、いいダンサーの条件とは何でしょうか。
自分が自分らしくあるということ、
自分をわきまえて自分の奥深いところに内包することをキャッチする、
自分の感性を磨き、その集約したものを表現する、
自分のアイデンティティを早く見つけるっていうか、
自分の指針に忠実に向かっていく、
ということが大切でしょう。
でも現代では、コマーシャリズムに影響を受けて名前が売れたり劇場がいっぱいになったりすることと、その舞台を見て心が震えることとは必ずしも一致しないように感じます。
2月にはまたスペイン公演があるそうですが。
2月27日にフラメンコの揺籃の地ヘレスのフェスティバルにお招きいただいて、一昨年東京で上演したスペイン文学の大作「ラ・セレスティーナ」をやるんです。何十人も出るんでちょっと大変なんですけどね。これはスペイン文学の中では「ドン・キホーテ」の次ぐらいに文学史に位置する作品で娼家の物語。そういう下世話なところもあるんですが、ロメオとジュリエットみたいな部分もあって、私はタイトルロールの金銭欲の固まりみたいな老婆の役を踊るんです。聖俗併せ持ったドラマチックな作品です。
2月にはダンス・マスターの主役の舞踊手も来日して、舞踊団のメンバーたちも身体がなまらないようにレッスン、リハーサルをスパルタで(笑)。
観客のためにも後進のためにも、どうかこれからもずっと舞台に立ち続けてください。
それは、私も願っていることですけど(笑)。

「カディスの女」をやってから大きなショールを集め出して、20枚ぐらいになりました。それを使っていくつか作品もつくったり。機械刺繍も手刺繍もありますが、昔の手刺繍ものは重さがありますね。
もうひとつ集めたのが人形で、これはフランスのジュモーのアンティック・ドールです。1960年から70年代、パリを行ったり来たりしている時、アンティック・ショップで買いました。いくつか持っていてそれぞれ表情も違うんですが、一番最初に買ったこの子が一番きれいですね。そうとう古いもので頭もちょっと曲がったり、買ったままでケースにも入れないから埃だらけなんですけど。新しくするとその妙味がなくなるので、服もリボンも昔のままにしてあります。色使いもおもしろくて、だいたいは生成りが多いですが、時代の雰囲気をもっているのがいいところかもしれません。
Q. 子供の頃に思い描いていた『夢』は何でしたか?
私を育んでくれた故郷は、徳島県の太平洋に面した県南、小さな漁師町牟岐町(むぎちょう)である。

うみは ひろいな おおきいな
つきは のぼるし ひがしずむ
うみに おふねを うかばせて
いって みたいな よそのくに
幾度も幾度も歌った、幼少期私の心を支えてくれた唱歌である。果てしなく広がる太平洋の海と碧く高い空、輝く太陽と冴えわたる月。海にも山にも恵まれた豊かな大自然の中 『海の向こう』にあるであろう空想(イメージ)の中に多感な少年時代の思いをはせたのである。
その未来の大きな『夢』は私を横浜から船に乗り、ナホトカからシベリア鉄道を経由してスペインまでフラメンコを求め旅だたせたのである。夢を叶えるということはなまやさしいことではない。沢山の試練や困難が待ち受けている。それでも勇気をもって夢に向かって行く強固な意志を持ち続ける事が人生を豊かなものにしてくれるのだ。と私は信じる。
Q. あなたのこれからの『夢』は何ですか?
―生ある限り舞い続ける『夢』に向かってー
『夢』は胸に大切にしまって大きくふくらませて行くものであり、スペインの格言でもある言葉
POCO
A
POCO
A
LO
LEJOS
(少しづつ遠くに…)という言葉がそのことを表している。
私の哲学となり生き方としても舞踊の中に実践している好きな言葉だ。フラメンコを始めて半世紀以上過ぎてしまった。とてつもなく長いようでもあるし、あっと言う間の出来事のようでもある。カルメン・アマヤの瞬間に空気を凝縮する力やアントニオ・ルイス・ソレールのアパッショネートな舞踊美あふれる至芸、私をフラメンコへ誘(いざな)って下さった歴史上の芸術家たち、また多大な愛を注いで私をフラメンコに向かわせて下さった諸先輩の愛の鞭を胸に秘め、フラメンコへの愛に生き続けたい。
昨年11月ユネスコの会議でフラメンコが無形文化遺産に登録された。アンダルシアという限定された土地に育まれた特殊な芸能であるが、特殊性が普遍性に通じることを身をもって立証して行きたいと思っている。フラメンコを通して世界中の人々の心と心を繋ぎ、心の豊かさを感じ合いたいと思う。ひたすら舞い続けることで『愛』と『平和』を伝え続けたい。これが私の描いている未来の『夢』である。