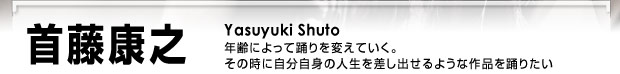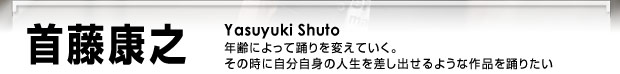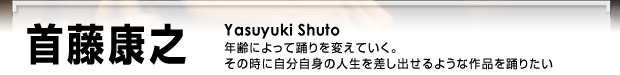神秘的パワーあふれる舞台に思わず吸い込まれ、劇場をあとにする時には心が爽やかさと幸福感に満ちている――首藤康之は私たちにそんな時間をもたらしてくれる数少ないダンサーだ。
鋭い感性と深い視座のもとに、彼が発する豊かな言葉。それはすべての若いダンサーへの贈り物である。
8月の神奈川芸術劇場では首藤さんの企画で夏期講習会が開かれましたね。
今回は初めての試みだったんです。去年まではクラシックのレッスンのみだったんですが、今年からはコンテンポラリーの中村恩恵さんとマイムの小野寺修二さんにもお願いしました。
お二人に出会ったのは最近で、小野寺さんは6年前、恩恵さんは2年ほど前ですが、それから一緒に創作する中で、沢山のことを話しているうちに、僕自身の表現も変わっていったということがあったものですから。
生徒達がいきいきとしていて、まさにレッスンとは踊ることに直結しているものだと感じました。
クラシック・バレエのレッスンは本当に基礎がだいじで、それが絶対的な基盤になっています。
様式美の絶対的なかたちがあって、それを尊重して毎日レッスンしなければならない。でもそればかりやっている中で、本来、始めた時の踊る喜びみたいなものを失う子供達も少なくないんですね。
そこでコンテンポラリーで動く楽しさを思い出してクラシックに戻ったり、マイムをやることによって身体全体で表現することを知ってもらうことで、またクラシック・バレエもおもしろくなっていくんじゃないか。
3つのクラスの行き着く先は同じなんですけど、今回はちょっと入り方を変えることで舞踊の素晴らしさ、身体表現を学んでもらいたい、と。
僕もずっとクラシックをやってきて、他のダンスをやる時に自分の身体を崩すということに抵抗と恐怖があったんです。コンテンポラリーは床に手をついたり転がったりしますが、クラシックではそれは失敗になりますから(笑)、なかなかクラシックの型を崩せない。
でもクラシックではない踊り、選択肢があるんだっていうことを早いうちから知っておくと、バレエを踊ることになっても全然違ってくるのではないかと考えたんです。

振付家モーリス・ベジャールが、かつてカンパニーの専属にと首藤さんを欲しがった時、首藤さんはベジャール・バレエに行ったら彼の作品しか踊らないけど、東京バレエ団では両方を踊れるからと日本に残ったんですね。古典とベジャール作品では身体の使い方が違いますが、初めてベジャール作品を踊った時にはいかがでしたか。
もちろん戸惑いました。
今は、振付家の方法で全部言われるとおりに動くという作り方はされていないんですね。ベジャールさんもこれはこうだと決めつけずに、ある程度の余白をつくってくださって、そこにダンサーが自分自身を入れていくという作り方でした。ダンサーには自分自身で考える力、音楽をとらえる力が必要で、それを持っていないといい作品は生まれてこないと思うんですね。
僕が今まで仕事させていただいた振付家たちは、いろんな意見やアイデアをくれましたし、僕自身の意見も聞いてくれて、ほんとうに共同作業をしているという喜びを与えてくれました。こちらは最初、遠慮していたんですが自分自身の考えを発信してこそ作品づくりなんだということを知りました。
ベジャール作品の「M」では、聖セバスチャン役で首藤さんは彼にインスピレーションを与えたことは、よく知られています。
もうベジャールさんはいないけれど、彼の魂は僕のなかの基盤になっていますから、僕がダンサーである限り生き続けると思います。
夏の講習会でも、僕が彼からいろいろ受け取って生かしていたことを、また次の世代に伝えていくこと。
それが僕の一番の望みなんだなということをいつも思っていました。
講習会で3つのクラスが終わったあと、センターが大事、イメージすることが大事だとおっしゃっていましたね。
そうですね、まずセンタリング。身体の中心軸がちゃんとしていなければダメということ。それから踊るためにはイメージすることが大事なんです。
今回、中学2年生の男の子が、何が重要だと思ったかというと”目”だ、と言ったんです。僕もそれを常に伝えたいと思っていたので、これは大きな収穫でした。
たとえば話す時も相手のどこを見るかというと目。お客様は目で見て感じていますがダンサーの身体のどこを見ているかというと、みんな目、顔って言う。クラシックのレッスンは自分自身との会話なんですが、マイムの稽古はコンタクト、対話なんですね。ミラーのメソッドでは鏡のように2人が一緒に寝て起き上がる、そこではお互いやっぱり目で空気感をつかんで動いているわけです。

この、目の重要性を僕はシルヴィ・ギエムと初めて一緒に組んだ時に習ったんですね。ギリシャでベジャールの「春の祭典」を踊った時に、相手がギエムさんですから僕はナーバスになっていて、彼女とどうやってコンタクトをとっていいのか迷って。リハーサル時間もほとんどなくて、1つだけ激しいリフトがあるんですが、若かったしアタフタしていたら「とにかく次は本番だけど、目だけははずさないように。そうすれば何が起きても大丈夫だから」って言ってくれた。本当にその通りでした。
素敵な経験ですね。
それで東京とギリシャの公演の全部がうまくいった。ギエムさんは、目の重要性をヌレエフから19歳の時に習ったと言っていました。
僕は古典バレエが好きで、回転や大きなジャンプ、長いバランスを見るとほんとに心が高揚するんですが、ダンスの舞台で、何が一番人の心に残るかというと、その人のパーソナリティや人生がどれだけ出ているかっていうことで、それを語るのはやっぱり目だと思うんですよね。
そういった意味で今回は、いい夏期講習会ができたと思いました。

首藤康之 Shuto Yasuyuki15歳で東京バレエ団に入団。19歳で『眠れる森の美女』王子役で主役デビューを果たし、その後『ラ・シルフィード』、『ジゼル』、『白鳥の湖』等の古典作品をはじめ、モーリス・ベジャール振付『M』、『ボレロ』他、ジョン・ノイマイヤー、イリ・キリアン等の現代振付家の作品にも数多く主演。
また、マシュー・ボーン振付『SWAN LAKE』では“ザ・スワン/ザ・ストレンジャー” /“ 王子”役で主演し、高く評価される。
2004 年、『ボレロ』を最後に東京バレエ団を退団、特別団員となる。以降は、浅野忠信監督の映画『トーリ』に出演、ジョー・カラルコ演出『SHAKESPEARE’S R&J』でストレートプレイに出演する他、東京バレエ団『牧神の午後』『ペトルーシュカ』『ギリシャの踊り』に客演。
07年には自身のスタジオ『THE STUDIO』をオープン。その後もベルギー王立モネ劇場にて、シディ・ラルビ・シェルカウイ振付『アポクリフ』世界初演。
小野寺修二演出『空白に落ちた男』に主演。
最近では『The Well-Tempered』『時の庭』等、中村恩恵との創作活動を積極的におこなっている。また、ドイツ・デュッセルドルフにて、ピナ・バウシュが芸術監督を務めるNRW国際ダンスフェスティバル、アイルランドのダブリン国際ダンスフェスティバル他、海外のフェスティバルにも数多く出演等、国内外問わず活動の場を広げている。
舞踊評論家 横浜市出身。早稲田大学卒業後、コピーライター、プランナーとして各種広告制作に関わる。そのかたわら大好きな劇場通いをし、’80年代から新聞、雑誌、舞踊専門誌、音楽専門誌などにインタビュー、解説、批評などを寄稿している。
ステージフォトグラファー 東京都出身。海外旅行会社勤務の後、舞台写真の道を志す。(株)ビデオ、(株)エー・アイを経て現在フリー。学生時代に出会ったフラメンコに魅了され現在も追い続けている。写真展「FLAMENCO曽根崎心中~聖地に捧げる」(アエラに特集記事)他。

神秘的パワーあふれる舞台に思わず吸い込まれ、劇場をあとにする時には心が爽やかさと幸福感に満ちている――首藤康之は私たちにそんな時間をもたらしてくれる数少ないダンサーだ。
鋭い感性と深い視座のもとに、彼が発する豊かな言葉。それはすべての若いダンサーへの贈り物である。
首藤さんは以前、踊ることは舞踊言語の旅をすることだと言ってらした。
先日、テレビではバリ島での踊りを拝見しました。
とても興味があったんです。バリの人たちはダンスを職業とせず、さまざざまな人たちが神に捧げるため、自分のために楽しみながら踊っていて、それが文化、生活になっている。それが自然でシンプルで、皆さん純粋な思いでやっていて、そんなに力が入っていないのにすごい踊りをするんです。
僕の先生は3歳から37年間踊っていますが、ご自分の「バリス」という男の踊りをまだまだだと言ってらした。僕も踊ってみてこの動きはバレエと似ているな、マイムっぽいなとか、すべてがつながっていると感じる瞬間があって、ほんとに舞踊って素晴らしいなと改めて感じました。

首藤さんご自身はバレエ・ダンサーになろうと思ったのはいつですか?
発表会で男の子1人だったんですが、「ジゼル」のペザントのヴァリエーションで舞台に立った時に決まった、という感じでしたね。
小学5年生でしたが、出る前に身体の血液が全部取られてしまったというぐらいに緊張して(笑)。
でも舞台に一歩踏み出して、ライトが当たってお客さんの目がこちらを向いて音楽が鳴ると、その血がどんどん戻ってきてすごく自由になれたんですね。
恐怖がどんどん快感に変わっていくというような、言葉ではうまく言い表せないんですけれども、もう何にも変えられない瞬間だなと思って。
それは今でも同じで、本番前は何かに頼りたいぐらい緊張するんです(笑)。
優れたパフォーマーは皆さんそう言います。でも、いったん舞台に出ると解放される、と。
そういう人でないと観客を感動させられないのでは。その人が解き放たれるのを見て、客席は快感とか一体感とか浄化を味わう。ダンサーが舞台に出る前と後で変わらないことのほうが、不自然なのかもしれません。
そうですね、なんというかわからないけれど、踊っている時、舞台で表現をしている時がやはりほんとの自分というか、お客様が一番僕のことを僕自身よりも知っているような気がしますね。
バレエはご自分から習いたいと?
自分から言いました。きっかけは小学2年生で見たミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」。森重久弥さん主演の舞台でした。大分文化会館は僕にとっては初めての劇場体験で、チケット切ってもらってホワイエから客席に入って、緞帳があって暗くなると、線を引いた一歩先に全く自分の世界とは違う世界が繰り広げられている。なんてことが起こっているんだろう、と。もちろん小2ですからユダヤの話はほとんどわからなかったんですが、不思議な感覚にとらわれて、ここはすごくいいなあと思った。
ある日、小学校の友達の発表会を見に行くと、あのミュージカルと同じ舞台でみんな踊っている。バレエを習えばここで踊れるんだって思ったんです。
ニューヨーク行きもご自分から?
はい。バレエを習って以来、僕は稽古も、劇場っていう空間も大好きになった。今でも劇場は一番落ち着く場所なんですけど、その頃には、毎日稽古があって毎日劇場で見られれたらいいなと思って。
当時は外国といえばアメリカで、福岡のアメリカ領事館に行って情報を得るという時代でした。ニューヨークへは11か12歳の頃に1人で初めて1週間行きました。小さなホテルをとってもらって、今は治安が良くなりましたが当時は怖くて。着いたらいろんな人が話しかけてくるからトランクには名前を書かない。タクシー乗り場に直行して、証明があるのを確認してイエロー・キャブに乗るとか。
いろいろ僕なりに調べて、オープン・クラスも受け、劇場にも行きました。ただ、シーズンじゃなかったのでその時はバレエはほとんど見られなかった。それで毎日タイムズスクエアで並んでチケット買って、ブロードウェイに行ってミュージカルを見ました。
11,2歳の少年が1人で! ご両親もよく送り出してくださいましたね。
そうですね、全部自分でやるなら行ってもいいってことだったんで。その後もコネチカットにあるハートフォード・バレエのサマー・スクールに行ったりしていましたね。
学校では首藤君はバレエをやってる男の子っていうふうに見られていたんですか。
最初は恥ずかしくてやっぱり隠していましたね。あえては言わないようにして。
だけど胸のなかには踊りに対する情熱がフツフツとわいていたわけですね。
もう日に日に増す一方で(笑)、好奇心を抑えることもできず。
東京バレエ団に出てきた時もそうだったんですけど、何かやりたい時には本能的に感じたまま行動してきました。それは今でも変わらないですね。「アポクリフ」を振り付けたシディ・ラルビ・シェルカウイも、琵琶湖ホールで行われていた「ダヴァン」という作品の広告がすごい素敵で、時間があるから行って観たんです。
それはそれは素晴らしいパフォーマンスで、そこから彼とコンタクトをとるようになり、ベルギー王立モネ劇場での初演につながっていきました。いろんなことを知らないと、こうなりたいという思いもわいてこない。子供の頃から芝居やコンサート、映画とか劇場に通っていろいろ見たり感じたりしてきたことが、僕のベースになっているんだと思います。
ところで身体の表現芸術であるバレエには、ある程度の年齢にくるとたとえば古典は踊れなくなるということがありますが、どうお考えですか。
そうですね、古典バレエには踊れないものもありますし、踊る必要もないのかもしれませんね。
僕も、自分自身が踊るレパートリーとこれからやっていきたいダンスというものに少しズレが出てきていたので東京バレエ団を離れました。もちろん1つの踊り「白鳥の湖」をずっと一生踊り続けるという考え方もあってそれはそれで素晴らしいと思う。僕自身はやはり年齢によって踊る作品を変えていきたい。
その時に自分自身の人生を差し出せるような作品を創作し踊りたくなったんです。

中村恩恵さんとはどのように出会われたのですか?
最初、恩恵さんは踊らないけど彼女の振付作品に出てくれませんかと言われたんですね。
その時は僕自身がちょっと作品のキャラクターに合わないと思ったので、お断りしたんです。
あんな断り方したからもう連絡はこないかなと思ったら、その1か月後に神奈川芸術舞踊協会でデュエットをつくる企画があるので一緒に踊っていただけませんかと誘ってくれました。
それで創作を始めたんですけが、初めは2人ともすごくナーバスではあったけど創作の最初の段階から音楽を聞いて、一緒に手を取り合って動く感覚が心地よくてまったく違和感がなかったんですね。
同じ音楽を聞いて同じことを同じ瞬間に考えていることがよくあって。そしてやっぱり素敵なデュエットができました。創作には女性の力は絶対に必要ですが、彼女とだったらそれだけじゃなくジェンダーを越えてもいろんなものをこれからつくり出せるんじゃないかとすごく感じています。
デュエットの「The Well-Tempered」、横浜で拝見しました。これまで違う人生を歩んできたダンサー2人の間に何が生まれるかというスリルがあって、踊りに対するストイックでピュアな姿勢がおふたりとも似ているのを感じました。今度またおふたりで新国立劇場で「ソネット」を踊られるんですね。
はい。今回はシェイクスピアという偉大な劇作家のものなので、あまり抽象的な作品にせずに、具体的で演劇的な作品にしたいなと思いまして。ソネットっていうのは愛の詩ですが、この世の中にはいろんな愛のかたちがあると思うんですよ。母性愛もあれば友愛も兄弟愛、もちろん異性の愛、同性愛、いろんなかたちがある。そういったさまざまな愛のかたちをシェイクスピアの書いた詩で表現できたら、と思っています。

神秘的パワーあふれる舞台に思わず吸い込まれ、劇場をあとにする時には心が爽やかさと幸福感に満ちている――首藤康之は私たちにそんな時間をもたらしてくれる数少ないダンサーだ。
鋭い感性と深い視座のもとに、彼が発する豊かな言葉。それはすべての若いダンサーへの贈り物である。
首藤さんにとって、ダンサーであること、それを継続することの条件はどんなことだと思いますか。
20代の頃は、なんで40歳になって踊っているんだろうって不思議に思ってました。
実際に自分がその歳になると、同い年のバリ島の先生もおっしゃっていましたが、肉体的な衰えっていうのは実はあまり感じてないんです。舞踊に対する考え方が深くなればなるほど、表現することもすごく楽しくなった。でもやっぱり演じたり表現したりすることはとても勇気がいることなんですね。理解が深まれば深まるほど怖くもなるし、勇気ももっと必要になるんですけど、でも表現することによってもっと自由になる。それにはシンプルに、正直になるってことでしょうね。
正直ってむずかしいことですね。
とてもむずかしいですね、シンプルで正直であることっていうのは。1人だけならいいのでしょうけれども、いろんな人と共存していて、いろんな社会、文化や宗教もあるところで生きていますから。情報も過多で人間関係も複雑になって、シンプルではいられない正直ではいられないという瞬間も出てくるわけですね。だから勇気も必要なんです。
昔はよく、体型のキープとか肉体的衰えとかを考えて、年を重ねるのはとても怖かった。以前より跳べなくなってはいるんでしょうけど、感覚としてはそれほど感じていなくて、常に肉体的にも精神的にも進化しているような気がするんです。ちゃんと稽古していればキープするのはそれほど難しいことではないです。それ以上に進化させるというのはとても努力が必要だと思う。でも僕はそれも今は楽しんでやっていますけど。

今、世の中にはネガティブな空気があふれています。
首藤さんのなかに、もしネガティブな感情が生まれた時、首藤さんはそれをどういうふうに取り払いますか?
もちろん人間ですからネガティブな感情をもつことはありますが、そんな時には、どうして自分がここに立っているのか、ほんとうに何をやりたいのかを考えますね。
昔から何かにぶつかった時は、稽古をもっともっとしています。基本レッスンをすごくする。
ネガティブになるっていうのは何か自分自身の軸からはずれた時とか、自分自身を見失った時ですよね、だからほんとに自分が何をやりたいのかってことをちゃんと思い出して、ふつうに基本練習をすることでだんだん本来の自分に戻っていかれるっていうことはあると思います。
最後に、最近、踊り以外のことで感動したことはありますか?
毎日感動してます(笑)。美味しいもの食べれば感動するし、舞台も毎日発見の連続で。
たとえば今日レッスンしていても新しい身体の使い方とか感じ方を知って、40年も生きてきてどうして気づかなかったんだろうとか。
だから僕は自分の身体と今も会話中ですね、うまくいく時もあればいかない時もあって、とにかく話して話して話し続けなきゃいけないな、と。僕自身の身体と僕とは別物なんです。
そこでうまい関係を築くために、いろんなものを見たり感じたりしているということですね。

このニジンスキーのブロンズは、僕が東京バレエ団を2004年4月1日、退団する時にバレエ団の団長、佐々木忠治さんからいただきました。もともとは佐々木さんがベジャールさんから贈られたもので、「あなたが持っていたほうがいいんじゃない」と僕にくださった。
バレエ・リュスの時代のブロンズで、ニジンスキーが踊ってセンセーションを巻き起こした「バラの精」で、すごい貴重なものだと思います。もちろんニジンスキーという人には会ったこともないのですが、あの有名な写真を見るだけで、自分だけの頭の中の劇場で彼が踊り出すような感じがします。僕達ダンサーだけじゃなくて、街を歩いている若い人でも、ニジンスキーの名前だけは知っていたりする。これはすごいことですね。
バレエ団を退団する時に、佐々木さんから「いろいろ教えてね」と言っていただきました。僕自身もやめる時に、踊ってきたレパートリーや振付家から直接教わったことを伝えていきたいという思いがありました。今はベジャールさんに会ったことのない団員が3分の2ぐらいになりましたし。
今度は、キリアン さん の作品で指導に行きますが、伝えることを大事にしていきたいと思います。
Q. 子供の頃に思い描いていた『夢』は何でしたか?
劇場に住むこと。
Q. あなたのこれからの『夢』は何ですか?
一つ一つ丁寧に、責任を持ちながらダンスの創作活動に関わり続けていき、それを通して社会とつながりを持っていきたい。
中村恩恵×首藤康之
『Shakespeare THE SONNETS』
中村恩恵と首藤康之がシェイクスピアの『ソネット』を現代の視点で読みなおしたデュオ作品を新制作します。
豊かな芸術性を持つ二人のアーティストが作り出す豊かな空間は、幅広いお客様にダンスをお楽しみいただける機会となるでしょう。
日程:2011年9月30日(金)19:00 / 10月1日(土)18:00
会場:新国立劇場 中劇場
構成・演出:中村恩恵 / 首藤康之
振付:中村恩恵
出演:中村恩恵 / 首藤康之
衣裳協力:ヨウジヤマモト
全国公演について
兵庫県立芸術文化センター 2011年10月15日(土) 14:00開演
お問い合わせ:芸術文化センターチケットオフィス
TEL:0798-68-0255 http://gcenter-hyogo.jp/