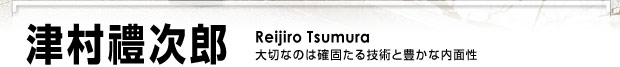相手の心を包み込むような温かい眼差し、説得力をもった響く声。年齢、踊り、芝居、音楽のあらゆる垣根を超え、文字通り八面六臂の活躍を続ける津村禮次郎氏は舞台芸術を牽引し続ける。
津村氏が語るダンス、能、師匠との出会いには、すべての表現者へのメッセージがこめられている。
舞踊も近年は、さまざまなジャンルの方によるコラボレーションが盛んに行われていますが、津村さんのように、お能の世界から参加されている方はなかなかいらっしゃらないですね。
客演で能をやられたりしても、作品全体に関わるってことはあまりないですね。
秋に初演された新国立劇場の「パゴダの王子」でも、津村先生のご出演を楽しみにしていた舞台ファンは多かったと思います。
あれは5月でしたか、アイデアの段階で芸術監督のビントレーさんにお会いし、部分的なリハーサルをしました。結局、本格的には8月の後半から2ヶ月ほどで2時間の作品をつくることになって、音楽とのなじみの問題もあり、なによりも練り上げていく時間がなくなってしまいました。
それで記者会見の翌日ですが、稽古が始まってまもなく、ビントレーさんと話し合いがあり、私から降りますと言わせていただいたんです。でも、「和」の作品だからとアドバイザーとして参加するように要請されたので、振付でも立ち回りのシーンなど
長刀
の使いをアレンジしたり。着物姿で酔っ払う退廃的なシーンでは、ダンサーたちが衣裳をきちんとしていて酔っ払っているふうに見えないんです(笑)。
それで片袖を脱いででしどけなくするにはどうするか、そういう細かいところまで指導しました。
それはダンサーにとっても、たいへん貴重な経験だったと思います。
ビントレーさんからは、演出上、作品全体の流れのなかで遠慮なくなんでも言ってほしいということでしたので。打ち上げではダンサーのみんなも喜んでくれました。
スタジオアーキタンツ
10周年記念公演より
11月には、スタジオアーキタンツの10周年記念公演で「トキ」を拝見させていただきました。
先生が中央にスーッと進み出たり、横に移動したとたんに空気がパッと変わって。本来、そういう空気が舞台から客席に伝わるには劇場の大きさに関係して、限りがあります。
私は客席の後ろのほうに座っていたんですが、迫ってくるような力を感じました。それは何十年と能舞台に立っていらっしゃる津村先生の強烈な存在感、オーラのなせるわざだと思いました。
能は、照明にたよらないで身体だけで表現しなきゃいけないから、今まで習得したものが身についているのかな。少しは違ってくるのでしょうか(笑)。
「トキ」は以前に津村さんがトキの再生を願って発表された創作ですが、これをもとに今回は小尻健太さんが再構築したとのこと。それは、幻想的で味わいのある舞台になっていました。先生はお能の声と面を使っていらして、なんとも言いがたい不思議な時間が流れていました。
僕は楽しみながらやれました。小尻健太君が僕の作品をよく勉強して、能の「トキ」は佐渡で初演したので、彼も一人で佐渡に行って見たりしたようです。7月くらいから作っていますから作品がだんだん変わってくるんですね。
もともと僕は佐渡の村人みたいな役でしたが、最終的には能楽師という役で次第に抽象化された存在になりました。で、ああいうからみを、パ・ド・ドゥを(笑)。
あの酒井はなさんとのパ・ド・ドゥも本当に素敵で。客席も楽しんでいました。
先生はいろいろなステップで踊って、パ・ド・ブーレまでしていらした。
パ・ド・ブーレは能では「流れ足」といって、妖精を表したり、水の上を流れる、霊的な存在を表現したりするんです。はなさんとは前に「ひかり―肖像」で共演して何回も踊っています。彼女は”ため”がきくんですね、私たち能役者はリズムをカウントしてパッと出られない。パッ、のあとに
間
がある。
間の取り方が重いんですね。彼女はそういうことも包み込んで、バランスもしっかりしていますね。

コラボレーションを具体的にうかがいますと、「トキ」の場合はミーティングを重ねていって、ここはこうしようという風に作っていったのですか?
パーツごとの場合もありますし、全部最初から出来てくることもあります。小尻君の場合には無に近いところから始まって、パーツから始めて作品のコンセプトを作りあげていく。森山開次君もこれまで一緒に舞台やってきましたが、彼は最初から自分で図面書いて全部出来ていて、稽古を始める時にプレゼンができるんですね。ただそれは途中でどんどん変わる。そこに僕がアイデアを出したり、やるだけのことはやって中盤から消していくというやり方ですね。最終的には音も削りながら何回かやって作り上げて行く。
今回の「トキ」ではパーツを作りながら話し合いをしながら、踊りをつくっていきました。はなさんとのパ・ド・ドゥも、やってみましょうか、と。僕がはなさんをしっかりホールドしちゃうもんで、そんな握らないでとか(笑)。
能の所作のように腕を出すと、そこにはなさんがバレエの身体で動いてきてぴったりと決まる。僕の能の要素と交わる。まさにそんな感じでした。
大いに勉強になりましたし、夢が叶いましたね。
うかがっていると、そういうやりとりがとても楽しそうですね。
同じ舞台に立ったらアーティストとしてイーブンだし、同じ経験値からものを言います。
だから、自分の直属の先生のことは先生と呼びますけど、津村さんとか禮次郎さんと呼ばれるほうがうれしいですね。

津村禮次郎 Reijiro Tsumura 観世流緑泉会代表 重要無形文化財(能楽総合)保持者
社団法人日本能楽会・社団法人能楽協会会員
二松学舎大学文学部特任教授
一橋大学社会学部講師(2009)
1942年福岡県北九州市に生まれる。
1964年一橋大学経済学部卒業。
1969年同社会学部卒業。
在学中に女流能楽師の草分津村紀三子に師事。
卒業と同時に能楽師の道を志し先代観世喜之に師事。
1974年津村紀三子死去により緑泉会を継承する。
1963年能「花月」初シテ。
1971年能「道成寺」初演。
91年文化庁により重要無形文化財(能楽総合)保持者に認定される。
年4回の緑泉会定例公演(喜多能楽堂)のほか、79年小金井薪能を作家林望氏等と設立、本年28回を迎える(8月20日 都立小金井公園内)。
舞踊評論家 横浜市出身。早稲田大学卒業後、コピーライター、プランナーとして各種広告制作に関わる。そのかたわら大好きな劇場通いをし、’80年代から新聞、雑誌、舞踊専門誌、音楽専門誌などにインタビュー、解説、批評などを寄稿している。
ステージフォトグラファー 日本写真芸術専門学校 広告・肖像科卒業後株式会社エー・アイに入社。飯島篤氏のもとで舞台写真を学ぶ。幼少時より習っていたクラシックバレエを中心にコンテンポラリー等多くの公演の撮影を経験。現在フリーで活躍中。

相手の心を包み込むような温かい眼差し、説得力をもった響く声。年齢、踊り、芝居、音楽のあらゆる垣根を超え、文字通り八面六臂の活躍を続ける津村禮次郎氏は舞台芸術を牽引し続ける。
津村氏が語るダンス、能、師匠との出会いには、すべての表現者へのメッセージがこめられている。
津村先生とのコラボレーションで若いダンサーたちは沢山の発見があると思いますが、津村さんも発見はおありですか?
あります。バレエと違って能役者は発声とか身体表現の明確なメソッドがないわけです。真似しろと言われて、小さい先輩から大きい先輩、最後は師匠まで何段階も怒られて覚えていく。
肝心のところを教えていくということがなかなかないんですよ。バレエのクラスを端で見ていたりすると、筋肉とか軸とかを解剖学的に教えていらっしゃるのがとても参考になります。
安田登さんというワキ方の能役者といつも一緒に舞台に出ているんですが、彼はロルフィングを研究して本も出しています。たとえば上半身と下半身を固定していくには大腰筋が大切といったことなんですが、舞台上で筋肉の使い方、いい身体というのを見ていると、それが僕だと言うんです。それで僕にモデルになってくれ、と。僕は安田さんのような勉強をしてきたわけではないので、たまたま師匠から僕の身体の欠陥を指摘されて直してきたんですね。バレエの方から細かい説明を聞くと、もういっぺん動きと筋肉の関係を分解して組み立てていくことができるので、自分でもそれを意識してやっています。
先生は本当に背筋も動きもすべてお若い!私事で恐縮ですが30年前に
仕舞
と謡(うたい)を初めて習った時、基礎レッスンなしにいきなりレパートリーを覚えるように言われてびっくりしました。
そうなんですよ、もう少しメソッドというか、運び、立ち居振る舞い、どこから始めるかメソッドがあれば稽古しやすい。僕らワークショップを海外でやるんですが、この前も一ヶ月モスクワに行きました。その時はまず、正座している姿が立ち姿に共通していくってことから始めます。
足をきちんと組んで、身体の角度を少し前傾、っていう。これを最初に教えるんですね。ただセイザというかたちをつくらせる、で、お辞儀、礼ってやる。お願いします、終わったらありがとうございます、と必ずやる。またこれが日本の文化の紹介にもなり、彼らもすごく喜んでくれました。

当時は婦人能と呼ばれていましたが、津村さんのお母様、津村紀三子先生はその先駆者です。
能は男性が演じるものとされていた時代に、女性の能楽師としては大変なご苦労がおありだったと思います。
婦人能。そういうふうに言われていましたね。
彼女自身は、芸というのは男も女もなく天地のものだという考え方でしたね。もともと観阿弥が
曲舞
を取り込んでくるときには乙鶴という女性の曲舞師に教えを受けたとか、江戸時代には遊女たちが女能をやってきたということもありましたね。
だから武家式楽自体が男性のものとしてきましたけど、根本的なところでは女を拒絶する理由はない、と考えていました。僕も最近はそう思うようになったんです(笑)。
女性がお面をつけて能をやると弱いし、衣装も重たいですから、そういうハンディのある身体をどういうふうに使うかを師匠は僕に伝えたという…。彼女のすごいところは、本来だったら女性だから、後継者には女性を選ぶものだと思うんですね。僕自身もそう思っていたし、僕は実子ではありませんし末弟でしたが、彼女が最終的に自分の芸を僕に託して。その時はおおいに迷惑だったんですけどね(笑)。
私は、津村さんがお子さんの時から実のお母様に習ってらしたとばかり思っていました!
養子です。津村紀三子夫婦には子供がいないので。僕は10代からバレエもオペラも歌舞伎も見るのは好きでしたが、大学生になって初めてサークルで能を始めたのです。で、4年生の時に学園祭の能でシテをやることになって、師匠の家で個人的な稽古をつけてもらうようになった。
仕舞を津村紀三子に、謡を大内正美(注:津村紀三子の夫)に習い、4年生の時には師匠の家に住み込むようになりました。
いわば内弟子というような。
はい、本当は就職するつもりだったんですが、1年間、能の勉強を本格的にやってみたくて、そのあと実社会に出てもいいと。そしてそのまま居座っちゃった(笑)。
でもすんなりいったわけじゃないんです。伝統のお家に生まれた方は、楽屋に来たらどうするかとか道順はわかっていますから、うまくいく。僕たち外から来た人間は、何するにもすべて覚えなきゃいけないのですごいプレッシャーで、舞台に上がるにしてもとても不自然な状態で上がっていきますから。そういうことが10年ぐらい、30歳ぐらいまでは続きました。

やめようと悩んだりなさったことは。
3回ぐらい、やめようかなと思ったこともありましたね。
有名な話ですけど、僕の家出事件というのがあって(笑)。
師匠のところから家出を。その時はどんなことをなさっていらしたんですか?
実は能は嫌いじゃないので、能をやっていきたいとは思っていたんです。先輩達が大勢いて、津村自身は隠居する気持ちなっていましたが、僕が来たので後継者にする、と。
実家はもちろん反対、いろいろ社会的な問題もあったりして、僕もそれはなりたくないと思って26歳の時に逃げ出したんです。その前からお寺に縁があって、尊敬しているお坊さんがいる伊豆の仏現寺に行き、寺男をやっていました。それでも結局、津村の芸はすごく好きだったので、これをやるしかないか、と。ただ、家を継ぐという感覚が僕にはないんですね、普通のサラリーマンの家の子供ですから。やっと最近、そういうものから解放されたという感じがあります。
紀三子先生は素晴らしい師匠でいらしたんですね。
男も女もない、と彼女は言っているわけなんですね。彼女の考え方、それが今やっと僕もわかりました。

相手の心を包み込むような温かい眼差し、説得力をもった響く声。年齢、踊り、芝居、音楽のあらゆる垣根を超え、文字通り八面六臂の活躍を続ける津村禮次郎氏は舞台芸術を牽引し続ける。
津村氏が語るダンス、能、師匠との出会いには、すべての表現者へのメッセージがこめられている。
これまでさまざまな舞台に関わっていらっしゃいますが、若手のダンサーをご覧になっていて、先生がお感じになることは?
若手のダンサーをそんなに大勢は存じ上げないけれど、クラシック・バレエはトップにいく人も二番手、三番手の人もテクニックはすごいなと思います。ではトップに行く人は何が違うのだろうというと、やっぱり教育の場がトップに行く人ほど与えられていくし、より技術が身について更に良くなっていく。
それから華といいますか、これは持って生まれたものかもしれませんが、でも、僕なんか若い時に華のある役者じゃなかったですから。それを存在感といってしまえば、現代的になってしまうかもしれない。やってはいるんだけど、組織の中の1つのコマとしてでしかやっていないということではなくて、個として在る、と。そういう育ち方をして欲しいなと思いますね。
教育の力も大きいですね。
パリ・オペラ座のバレエ学校を2回ほど行ったことがありました。指導されているクラスを見学させてもらいましたが、校内ですれ違っても、食堂でも生徒たちのマナーがすごくいい。知らない人が来た時の挨拶や態度、それがきちんと教育されているんですね。ダンサーもいわば芸人ですからある種、接客、サービス業でもありますから、対人関係でどどのようにしなきゃいけないかを知らないと。向こうは頭をすっと下げて、きちんと挨拶する。やっぱりバレエは貴族社会で生まれたものですから。能も庶民芸だったけど、貴族武士の社会に入っていきましたからやっぱり挨拶にはうるさい。だから芸人は、下から上まで自分の身分に関係なく誰にでも対することができないと。それには教養も必要です。だから厳しいことを言うと、日本人は舞台でなかなかプリンスにならないし、見えないんですね。
それは本当によくいわれることですね。舞踊家に対して、先生は何を期待されますか?
僕はね、やっぱり技巧ではなく技術だと思う。身体を使うこと。それから自分を客観的に見る力を持つこと。技術ができるようになると、どうしても技術に溺れて自己満足になっちゃうんですね。


この言葉は僕の宝になっているんですが、大学の時、ゼミの村松祐次先生にかわいがっていただいて中国経済の研究を手伝っていました。僕が古典に行くとなったら先生から「能を創れ」って言われたんです。能を創るようになれ、と。
そして津村紀三子は、突然72歳で心臓発作を起こして一週間ぐらいで亡くなったんですけど、呼ばれた時の最後の言葉が「もう教えた、能は創れ」と。能をじゃなくて、能は創れ、と。
彼女はその翌日死んだのですが、それは僕にとってすごい保証なわけです。
自分をここまでを作り上げてくれたんだ、あとは自分で創るということなんだ、と。
彼女は女ですから自身はここまでやってみたけれど、おまえは男だからもう一尺深く掘れ、と。創ること、アーティストはやっぱりそこに視点を持つこと。
僕は若いころは古典の方がいい、師匠が創作をやっているのがいやでいやでしかたなかったんですが、40半ばになってそれに気がついた。


僕が一番悩んでいた時期ですが、昭和42年に身延山の修行の道場に行って修行をしたんです。得度も在宅でできるんですが、日蓮宗の僧侶としてはどんな偉い坊さんでも、この身延山で修行しなければならない。修行が終わると先生に色紙を書いてもらいます。当時は70歳の清水玄正という方がこの観音経を書写されて、僕の旧姓の大内禮次郎の為書きを添えて送ってくださった。日蓮が佐渡へ流罪になったことを、津村紀三子が「法難」という創作能にしましたが、たまたま伊豆の伊東の仏現寺というところに行った時に、そこで出会ったお坊さんが素晴らしい方だった。それで家出の時にこのお寺で僕は寺男みたいなことをしていたわけです。その後友人の僧たちと佐渡に行脚に行き、お寺と縁ができて、毎年、佐渡では学生を連れて合宿しています。
それからこれは高麗青磁です。高麗青磁はもともとグリーンが濃いのですが、僕はあまり好きじゃなくて、たまたま別の用件で韓国に行った時に、人間国宝といわれている池順釈という方の作品に出会いました。その色あいが好きになって、その時は窯元までバスで行きましたが、お祭壇があって、一ヶ月前に亡くなられた、と。それで旅先ですから大きなものは買えないので、その時は小さな水差しと水滴を買いました。この高麗青磁はその時手に入れたものです。焼き物は磁器だけでなく土ものも好きです。お飲みいただいた茶碗は群馬の月夜のほうで窯をもっている僕の友人が焼いた湯飲みで、これは佐渡で買った赤土の無名異焼のものです。
Q. 子供の頃に思い描いていた『夢』は何でしたか?
小学生の時は小学校の先生。
高校生の時は画家か建築デザイナー。
Q. あなたのこれからの『夢』は何ですか?
自分については特にありませんが、日本の文化がもっと豊かになることかな。

相手の心を包み込むような温かい眼差し、説得力をもった響く声。年齢、踊り、芝居、音楽のあらゆる垣根を超え、文字通り八面六臂の活躍を続ける津村禮次郎氏は舞台芸術を牽引し続ける。
津村氏が語るダンス、能、師匠との出会いには、すべての表現者へのメッセージがこめられている。

技術というのは、身体を支えるもの。技巧はこざかしさとか、あざとさに通ずるものですね、スタンドプレーをしたり、とか。
そうですね、雰囲気に流されてしまって。でも世阿弥はまた、その場その場で対応していくことも能役者として大切だと言っています、それも空気を読んで。
それには確固たる技術と精神性、内面の豊かさが求められる。そうしないと内容が詰まっていかない。
やはり若い時は、ほんとうに技術が必要だと思うんです。
技術がないと小手先の技巧でごまかしちゃう、それがわかってしまうんですよね。技巧に行かない技術というか、僕もバレエの32回転を見るのが気持ちよくなるくらい好きで、ここでバランス崩れたな、なんて思いながらいつも見ているんですけど(笑)。
でもそれを作品のなかで必然性のあるものにしていくには、もっと別のもの、内面の豊かさといったものが必要だと思います。
さきほどおっしゃった、自分の内から湧き出るものが必然性ですね。
稽古している時はほんとは湧き出るどころじゃないんですが(笑)、作品をやると決めた時、始める時には湧き出るものってあったと思うんです。今はあまりないですけど40代50代の頃はありまして、僕も来年これをやろうと企画しているときはすごく楽しい。
稽古に入るとだんだんつまらなくなって、自己嫌悪に陥り、リハーサルになるとなんでこんなの選んだかなあ、って(笑)。
でも本番になると違う。つまりそこに出たとたんに、意識も身体も違っているんだと思います。
そうですね。もう稽古したことを忘れてやらなきゃダメなんですね、逆にいうとそこまで稽古しなきゃだめということなんですね。それには身体という道具がちゃんとできていないとむずかしい、と。
そういう意味で技術というか身体能力というのは必要だと思いますね。

伝統と創造シリーズVol.4
『藪の中』
覆う、包む、塞ぐ、被せる……隠すという行為
かくすことで、むき出しになるもの。
同時にむき出しになり、かくれるもの。
日程:
2012年
3月8日(木) 午後7時30分開演
3月9日(金) 午後7時30分開演
3月10日(土) 午後6時30分開演
3月11日(日) 午後4時30分開演
会場:セルリアンタワー能楽堂
演出・振付・出演:島地保武
出演:津村禮次郎・酒井はな・小尻健太・東海林靖志
衣裳:maothu
音楽:熊地勇太
前売開始:2011年11月24日(木) 午前10時より
Bunkamura チケットセンター(03−3477−9999)
チケットぴあ(0570−02−9999)(Pコード:416-502)
カンフェティ(0120-240-540 http://confetti-web.com/