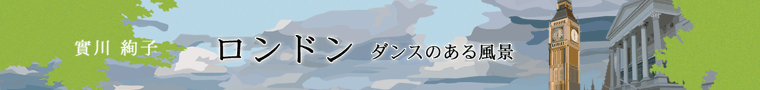Vol.5イン・ザ・スピリット・オブ・ディアギレフ
ニジンスキーが1913年に「春の祭典」を初演した際、それまでのバレエにはない革新的な動きを目の前にした観客は、半数が野次をとばし、半数は拍手喝采、反対派と賛成派が野次り合い、そのあまりの騒音にパリのシャンゼリゼ劇場は音楽が全く聞こえないほどの大混乱に陥ったと言われているが、私も今回の公演で生まれて初めてそれに近い衝撃的な舞台鑑賞体験をした。観客の五分の一程度が開始数分で席を立ち、中には「この作品はクズだ!」と叫ぶ者まで。残された観客は、作品を楽しもうとし、無理に笑い声を立てる者、カーテンコール時には「ブラボー!」と立ち上がる者の姿もちらほら。劇場内は始終、どう反応したらよいのかわからない観客の不安感に包まれていた。この日はバレエ・リュス誕生100周年記念公演として、サドラーズ・ウェルズ劇場のアソシエイト・アーティストである4人の振付家がそれぞれバレエ・リュスへのオマージュとして新作を披露したのだが、最後に上演されたハビエル・デ・フルートスの作品「Eternal
Damnation to Sancho and Sanchez」が、その前の3作品を全て忘れさせてしまうくらいのインパクトでもって、公演を文字通りかっさらってしまった。 |
|
 |
「Eternal Damnation to Sancho and Sanchez」の脚本は、ジャン・コクトーがバレエ・のために書いた作品からとられたもので、好色な背むしの法王と神父、妊婦姿の修道女たちが繰り出す悪趣味な物語。プログラムには、登場人物の説明と、馬鹿馬鹿しいほど複雑なあらすじが長々と書かれていて、途中で読む気も失せてしまったのだが、実際の舞台はもっとひどく、暴力、レイプ、流血、殺人、電気椅子による処刑など、舞台上で見たくはないであろうありとあらゆるものが、次から次へと容赦なく観客の目の前に突きつけられた。私も最初は、これほどまでに悪趣味なものを見たことがなかったためかなり動揺したものの、途中からここまで徹底して見せるからには、何かしらの意図があるに違いないと思うようになり、最後まで見守ろうと決めた(しかもフルートスはオリビエ賞も受賞している著名な振付家である)。初めは、ダンサーたちがお祈りの文句を唱える中で、目を背けたくなるシーンが延々と続き(この間ダンスらしいものはほとんどない)、この時点でかなりの人数の観客が席を立った。 |
その後、ラベルのワルツがかかり、ダンサーが踊り始めると、全観客が一斉に安堵と「これからやっと‘観るに値する’ダンスが始まるのだ」という期待を感じているのがひしひしと伝わってきたのだが、そのダンスが特に感心するようなものでなかったため、再び観客席は不安に包まれた。この辺りから、この作品がバレエの大胆な諷刺作品であることにようやく気付きだした観客が、それを誇示しようとしてか、不安を取り去ろうとしてか、大袈裟に笑い声を上げはじめた。 ここまでくればもう、劇場内で起こっていること全てが意図的なものであることはあまりにも明らかだった。前述の1913年の「春の祭典」初演での大混乱は、ディアギレフが観客を興奮させるために仕掛けた騒動だったという説が有力なのだが、フルートスのこの作品も、当時の騒動を再現するため、ディアギレフさながら巧妙に仕組まれた公演だったのである。このショッキングな体験そのものこそが、かつてその作品の斬新さで何度となく物議をかもしたバレエ・リュスへのオマージュであるに違いなく、カーテンコール時の半数のブーイングと半数の拍手喝采を聞きながら、私もやや「してやられた」感を感じざるを得なかった。ダンサーも、全力でこの悪趣味な作品にコミットしており、ここまで徹頭徹尾「ひどい」作品を完成させたことに対して、逆に感心すら覚えたほどだった。ただ、1913年との違いは、劇場が地震で揺れているかのような「大騒動」にまでは至らなかったということである。100年間の間に、あらゆる刺激が容易に体験できるようになり、連日の残虐な事件の報道に慣れた我々の感覚は、ずいぶんと麻痺してきてしまっているのかもしれない。 このフルートスの作品のお陰で、彼の作品の前に上演された3作品の内容は残念ながら霞んでしまったが、ランダム・ダンスのウェイン・マクレガー、ここでも取り上げたラッセル・マリファン、シディ・ラルビ・シェルカウィの3氏の作品もなかなか面白いものであった。シェルカウィの「Faun」はニジンスキーの「牧神の午後」を動物的な解釈で、マクレガーの「Dyad 1909」はマクレガーお得意の映像を組み合わせた科学的ともいえるアプローチで、スタイリッシュなダンスを展開。マリファンの「AfterLight」は、アルゼンチン出身のダンサー、ダニエル・プロイエットのソロが圧倒的だった。照明アーティスト、マイケル・ハルの、波のように揺らめく光の中で、無数の円を描くように旋回して踊るプロイエットは、陰影が印象的なニジンスキーのアイコニックな写真と、ニジンスキーが狂気の中で描いた幾つもの「円」の絵を髣髴とさせ、伝説のダンサーへのオマージュにふさわしい作品となっていた。 |
|
Vol.5イリ・キリアン&マイケル・シューマッハ「ラスト・タッチ・ファースト」
10月に入り、ロンドンもすっかり秋らしくなってきた。7~9月はシーズン・オフで閑散としていたロンドンのダンス・シーンだが、ようやく待ちに待った新シーズンが開幕し、それと同時に毎年秋の注目のダンス・イベント、「ダンス・アンブレラ」も始まった。「ダンス・アンブレラ」というのは、ヨーロッパ有数の規模を誇るコンテンポラリー・ダンスの国際フェスティバルのことで、毎年世界各国からさまざまなアーティストやダンス・カンパニーが参加している。昨年は日本から山海塾が参加し話題になった。 フェスティバル会場は、ロンドン各所。サドラーズ・ウェルズ劇場やオペラハウス、ラーバン・センターといったロンドンを代表するダンス専門劇場のほか、屋外でのパフォーマンスもあってバラエティ豊かである。ちなみに、屋外でのパフォーマンスで話題になっているのは、オーストリア人振付家、ウィリ・ドーナーによる「ボディーズ・イン・アーバン・スペーシズ」。カラフルな服に身を包んだダンサーによる「人間彫刻」が、ロンドン市庁舎前などに出没し、メディアにも大々的に取り上げられている。 |
|
 |
|
この日私が鑑賞したイリ・キリアンとマイケル・シューマッハの公演は、「ザ・プレイス」内のロビン・ハワード・ダンス・シアターで行われた。「ザ・プレイス」というのは、ロンドン・コンテンポラリー・ダンス・スクールの本拠地であり、私がよく利用する大人のためのイブニング・クラスやワークショップ、専門劇場まで揃ったロンドンを代表するコンテンポラリー・ダンスの中心地的な場所。英国随一のコンテンポラリー・ダンスの振付コンクール「ザ・プレイス・プライズ」も、毎年ここで開催されている。 日本でもおなじみのキリアンとシューマッハの公演は、チェーホフの作品にインスピレーションを受けたもの。ダンス作品というよりも、一見せりふのない演劇、もしくは動く彫刻のようなパフォーマンスは、連日超満員の人気公演となった。 蝋燭の灯が揺らめく中、チェーホフの作品からそのまま飛び出してきたような衣装に身を包んだ6人の男女が一室に集まり、客席のほうをじっと見つめながら静止している。しばらくすると、カードゲームをしている男たち、アルコール中毒風の女、未亡人、本を読んでいる女などが、そろりそろりと動き出す。ゆっくりゆっくりとワインを注いだり、テーブルクロスのしわを伸ばしたり、そのうちに男女間で誘惑しあったりと他愛のない戯れが展開するのだが、これもまた非常なスローモーション。あまりにもゆっくりで、物凄く大儀そうなことをしているように見えるが、実はたいしたことはしていない―というより、舞台上では実際何も起こっていない。これこそが、チェーホフが残した言葉「人生とはなんとつまらないものだろう!」に象徴される空虚な人生観にとりつかれながら、それでも自らの生きた証を残そうと必死にあがく人間のパラドクス、あるいは人間の愚かさであり、愛すべき点なのだ。6人のダンサーはそれぞれ孤独を抱えながら、ゆっくりとした、大して意味のない動きを繰り返す中で必死に生きる意味を見出そうとし、その点においてのみ、奇妙な連帯感を醸し出していた。まさに現実の縮図のようで、哀しいまでの滑稽さを感じるパフォーマンスだった。 |

實川絢子
東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。
東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.