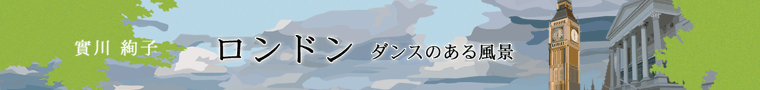Vol.12フュエル『エレクトリック・ホテル』
今、ロンドン中、いや国中のいたるところでイングランド国旗が翻っている。サッカー観戦のために仕事を早く切り上げる人も多く、通りを歩けばパブでテレビ観戦中の人々の歓声が店の外まで聞こえてくる。冬のオリンピックのときはちっとも盛り上がっていなかったのに、この国の国民のワールドカップへの入れ込みようはすさまじい。英国のプレミアリーグには世界各国の一流選手が在籍しているため、知っている選手同士が母国を背負って対決するというのも、これほどまでに盛り上がる理由の一因のようだ。
そんな、誰もがワールドカップ試合観戦のために家路を急ぐ中、私はキングスクロス駅で地下鉄を降り、再開発対象地区の寂れた空き地へと向かった。目的地は、線路脇に建つエレクトリック・ホテル。むき出しのコンクリートの建物の上に唐突に輝くネオン看板が、痛々しささえ感じさせる、裏ぶれた雰囲気のホテルである。ひと気のない通りを通ってホテルに着くと、一階のバーの明かりが、暗い空き地の中で虚構的な怪しさを放っていた。

怪しさを放つガラス張りのホテル
このホテル、実はダンス公演のために建てられた架空のホテルである。ロンドンでカルト的人気を誇ったパフォーマンス集団、SHUNTのディレクター、デイヴィッド・ローゼンバーグとドイツ出身の振付家フラウク・レクアルドがタッグを組み、長年の構想を経てようやく実現したダンス・ドラマ、『エレクトリック・ホテル』。運送用コンテナーを再利用して作られたガラス張りの建物の中で行われるパフォーマンスを、野外会場からヘッドフォンで音楽を聴きながら鑑賞するという画期的な試みに、ワールドカップ開催中にも拘わらず会場は超満員となった。
まず驚いたのは、ヘッドフォンを通して聞こえてくるサウンドのクオリティの高さ。開始直後、まだざわつく会場で、ザッ、ザッと誰かの足音が、まさに耳の後ろから近づいてくるのが聞こえてくる(あまりにもリアルで、実際誰かが来たのではと振り返る客が続出)。足音がやむと、「空室」のネオンサインが消え、最後の部屋に客がやってきたことが知らされる。
最後の客は、疲労しきった表情の赤いドレスの女。ホテルにはほかにも、隣室でアメリカン・インディアンの羽をつけてギターを弾く男、屋上階のプールで泳ぐ妊婦とそのパートナー、ベッドの軋みを無意味に楽しむ女、怠惰な清掃婦、レストランでおしゃべりにふける客などがいる。ありふれた光景のようであるが、青い箱を持ったバイク配達の男の出現をきっかけに、何かが、少しずつ、少しずつずれていく。限られた空間の中でのダンスは、腕を振り上げたり、その場での回転や跳躍など、ダンスと言うよりジェスチャーに近いものであったが、同じエピソードが、微妙に異なるジェスチャーによって何度も何度も繰り返されていく中で、段々と現実と非現実の世界の境界が曖昧になっていくさまは、さながらヒッチコックやデイヴィッド・リンチの映画を彷彿とさせた。赤いドレスの女が箪笥の中に入り込んだかと思うと、中から叫び声が聞こえてきたり、清掃婦がロッカーの中で飼っているらしい虎(吼え声だけが聞こえる)に餌をやったりと、不条理な出来事が展開されていく中で、各キャラクターの動きが段々と大きくなり、別々の部屋にいるキャラクターの回転や跳躍が徐々にシンクロしていく。
プールから上がって鼻をかむ音などのリアルで臨場感あふれるサウンド、別々の部屋にいるダンサーが同じ音に反応して動き出すタイミングの絶妙さ、そして怪しげなホテルの中の人々をガラス越しに〈覗き見〉しているような感覚、それらは舞台と言うより、リアルな映画を鑑賞しているような感覚に近い。
謎の光を放つ青い箱、赤いドレスの女の悲しげな表情、カップルの喧嘩、ロッカーの中の虎、叫び声、何一つ謎は解決されないまま、ドラマは突如エンディングを迎える。客は文字通り煙に巻かれたような、それでいて不思議な恍惚感につつまれて、怪しいホテルを後にすることになる。リアルに構築された不条理な世界の中に、むき出しの感情と動きを放り込んだ果敢な試みは、舞台芸術の新しい形を模索するこれまでにない革新的な形のパフォーマンスとして、静かに注目を集めている。

實川絢子
東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。
東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.