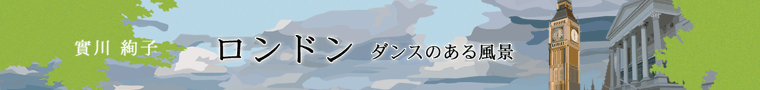Vol.20スコティッシュ・バレエ『欲望という名の電車』
テネシー・ウィリアムズの名作『欲望という名の電車』は、これまでにも何度かバレエ化されてきたが、今回のスコティッシュ・バレエによるバレエ翻案は、今までとは違う実験的な試みだった。というのも、振付家アナベル・ロペス・オチョアとともに、演劇界からシェアード・エクスペリエンス・シアターの芸術監督ナンシー・メックラーが監督として起用され、演劇とダンスの境界がどこまでもシームレスな物語バレエが目指されたのだ。
幕開きは、白いドレスを着た女が、暗がりの中裸電球の周りで手をはためかせながら踊るシーンから始まる。〈処女性と娼婦性を持ち合わせた白い蛾〉と例えられる主人公ブランチ・デュボワの生きざまを象徴するシーンであり、ブランチの脆い精神に重なるこの蛾のモチーフは、作品の中で何度も繰り返し登場する。この象徴的なシーンのあと、物語はほぼ原作に忠実に展開。結婚相手アランがホモセクシャルであることが発覚したあと、ブランチの絵に描いたような幸福の図は、舞台の上に積み上げられたブロックが崩れ落ちるのと同時に、一気にガラガラと崩壊していく。アランの自殺、そして生まれ育った美しい屋敷ベル・レーヴも手放し、全てを失っていくブランチ。夫アランを愛人から自分の元に引き寄せようとするパ・ド・トロワや、屋敷を失ったあとアルコール中毒になってホテルで行きずりの男たちを迎え入れていくくだりなどが、ミニマルでありながらリアルで刹那的な情感を伴うステップで語られていく。
二幕もまた、原作とほぼ同じ構成。故郷にいられなくなったブランチは、ニューオーリンズに住む妹ステラの家に転がり込み、自殺したアランの幻影に悩まされながらますます酒に溺れ、次第に現実と想像の世界の間をさまようようになっていく。圧巻は、ステラの夫スタンレーが、どこまでも上流ぶるブランチに対して怒りを爆発させ暴力的になったあと、映画版のマーロン・ブランドさながら「ステラ!」と絶叫するシーン。舞台上で突然発せられた台詞が唐突に感じられなかったのは、暴力シーンのダンスが既に声なき叫びと緊張感に満ち満ちていたためだ。スタンレーに恥ずべき過去を暴かれ、恋人ミッチとの結婚も反故になり、スタンレーに陵辱され、ブランチがついに発狂していくクライマックスも、ブランチははじめからそうされるのを望んでいたのではないかと思われるような、人間という生き物の悲哀が終始漂っていた。
終幕、再び無数の裸電球が暗い舞台を照らす。最後の望みであったステラにも見捨てられたブランチは、精神病院の医師にいざなわれて新たな世界へと出発する。舞台を埋め尽くす黒い衣装を着たダンサーたちが持つ赤い花は、死者への弔いの花。現実世界での死を宣告されたも同然の行く場のないブランチは、それが弔いの花とは気づかずに、無邪気に想像の世界の花畑の中を、蛾さながら一身に羽をはためかせながら飛んでいくのだった。
ピーター・セイレムによるオリジナル音楽は、ブランチの回想シーンに「イッツ・オンリー・ア・ ペーパー・ムーン」のモチーフを用いるなどジャズの要素を絡めながらドラマを効果的に演出していたが、やはりこの作品の成功の鍵は、戯曲における台詞に負けないほどの饒舌な身体表現がうまく引き出されていたことにある。オチョアの振付は、動と静を効果的に用い、決して大げさになることなくかつ情感に満ちた身体表現でもって、静の場面にあっても台詞が聞こえてきそうな緊張感溢れる劇的空間を作り上げることに成功した。
演劇界と舞踊界に生きるメックラーとオチョアによるこのコラボレーションは、観客がプログラムにある粗筋を読まずともクリアに筋を追っていける構成のクリアさ、登場人物の感情が台詞なくとも伝わってくる叙情的なステップによって、シンプルでわかりやすい、かつシンパセティックな新しい形の物語バレエを生み出した。この成功がきっかけとなって、またこの二人が別の物語を語ってくれる日が来るのを心待ちにしたいと思う。

東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。