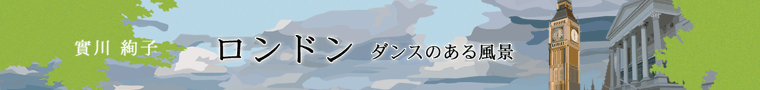Vol.21英国ロイヤルバレエ『パゴダの王子』
今週末は、エリザベス女王の即位60周年を記念するダイヤモンド・ジュビリー・ウィークエンド。祝祭日の少ない英国では珍しい四連休となり、英国王室一家の水上パレードをはじめ、コンサート、ストリート・パーティなど盛りだくさんのイベントが行われた。
街には英国旗ユニオンジャックが溢れ、国中が祝祭モードに包まれる中、ロイヤルオペラハウスで記念すべき週末の初日に幕を上げたのが、作曲も振付も英国人による全幕バレエ『パゴダの王子』である。振付は『ロミオとジュリエット』、『マノン』等のドラマティック・バレエで知られるケネス・マクミラン。亡くなる3年前に振り付けられた、マクミラン最後の全幕バレエである。音楽は英国を代表する大作曲家ベンジャミン・ブリテン。二人の英国随一の芸術家と、宮廷を舞台にしたハッピーエンドのおとぎ話――英国の記念すべき祝祭期間に上演するのに、これ以上ふさわしい作品があるだろうか。
しかしながら、『パゴダの王子』は色々と問題の多い作品でもあった。無名だった19歳のダーシー・バッセルを一躍スターにし、熊川哲也が道化役で活躍したマクミラン版の1989年初演のあと、ロイヤルバレエでは1996年に再演されたきりで、最近ではこのままお蔵入りしてしまうのではないかと囁かれていた作品なのだ。ブリテンが手がけた音楽は、インドネシアのガムラン音楽の要素を取り入れたバレエ音楽の傑作と言われる作品だが、複雑な筋書きのジョン・クランコ版(1957年初演)にもともと作曲された音楽は、そのままバレエ作品として上演するにはどうにも長すぎ、リハーサルにも時間がかかりすぎるのが難点だった。マクミランは、ブリテン側から音楽を一部カットする許可を得られなかったため、渋々全ての音楽に振りを付けたが、本人は最後まで納得できなかったという。
そこへ、今季で引退する芸術監督モニカ・メイソンが、最後に手がける作品のひとつとして、『パゴダの王子』が今後バレエ団の財産として残していくに値する作品かどうかを明らかにすべく再演を試みたのは、非常に勇気ある決断だったといえるだろう。そして今回16年ぶりの再演にあたり、メイソン監督は亡きマクミランの意思を汲んで計20分に及ぶシーンをカットし、ようやくマクミランが望んだ形での『パゴダの王子』を舞台にのせることに成功したのである。
物語は、一言で言うと、現代版『眠れる森の美女』。友人同士であったマクミランとクランコは、ともに戦後ロイヤルオペラハウスが再オープンするにあたって上演されたマーゴ・フォンティーン主演の『眠れる森の美女』に大きな感銘を受け、それがこの『パゴダの王子』のインスピレーションとなったと語っている。ただしどこまでも受動的なオーロラ姫は19世紀の価値観を体現した存在であり、だからこそ二人は、冒険を経て成長し、自らの手で幸せを掴みとるローズ姫を主人公として、20世紀に相応しい新しいおとぎ話を生み出そうと試みたのである。
バレエは、シェイクスピアの『リア王』さながら、エリザベス朝を髣髴とさせる宮廷で、年老いた皇帝が、領地を二人の娘に分割するところから始まる。皇帝がお気に入りの末娘ローズ姫に領地のほとんどを分け与えると宣言したため、嫉妬で怒り狂った姉娘エピーヌ姫は、ローズ姫の婚約者である王子を魔法でサラマンダーの姿に変え、王の従者たちを猿の姿にし、さらには皇帝から王冠を奪ってしまう。道化に導かれ、混乱に陥った宮廷を後にしたローズ姫は、自身の内面世界を象徴する旅の中で、虚栄や暴力性といった価値観を体現する四人の王を拒絶し、最終的にサラマンダーの潜む神秘的なパゴダの国へ到着する。サラマンダーに強い哀れみを感じ、冒険を経て精神的に成長したローズ姫のキスによって、王子は元の姿に戻り、エピーヌ姫が差し向けた四人の王を打ち負かして王冠を取り戻す。終幕、呪いから解放された宮廷で、晴れてローズ姫と王子は再び結ばれて大団円、という筋書きだ。
2日に迎えた初日のキャストは、主役ローズ姫に、ロイヤルバレエきっての高い音楽性と身体能力を誇る華やかなバレリーナ、マリアネラ・ヌネェス。故郷南米の太陽を髣髴とさせる、はつらつとした明るさが持ち味のダンサーだ。不規則なリズムで踊りにくいと言われるブリテンの音楽を難なく視覚化してみせただけでなく、トゥで立った軸足を曲げての連続回転など、複雑なパを正確にこなし、驚くほど高いグラン・ジュテで観客を熱狂させた。サラマンダーに姿を変える王子役のネーミア・キッシュは、地を這い回るような動きをするサラマンダーを見事に体現していたが、王子の姿に戻った後の最後のグラン・パ・ド・ドゥでは、スタミナが切れたのかあまり覇気がなく、完全にヌネェスの影になってしまっていたのが残念だった。皇帝から王冠を奪って虐待し、四人の王を誘惑する悪女エピーヌを演じたプリンシパルのタマラ・ロホは、研ぎ澄まされた剃刀のようなシャープなステップと、激しい感情表現が見事で、これ以上ない適役だった。他にも、西の国の王を演じたプリンシパルのスティーブン・マクレイの、くしゃみをしながらのコミカルな演技と難易度の高いジャンプ、道化役のアレクサンダー・キャンベルの軽快で敏捷なステップなど、ロイヤルバレエの層の厚さを見せ付けるキャスティングだったと言える。また、ローザンヌで入賞し、研修生から正式入団した金子扶生が、今回は三幕でソロを披露していたのも日本人ファンにとっては嬉しいサプライズだった。短いソロながら、シャープな足捌きと美しい上半身のラインで十分に存在感をアピールし、今後の彼女の活躍にますます期待が高まった。
『パゴダの王子』と言えば、日本では昨年秋に、デヴィッド・ビントレー振付による日本を舞台にしたバージョンが新国立劇場で初演されたばかり。ロイヤル・バレエ創始者の二ネット・ド・ヴァロアの悲願であった、作曲・振付ともに英国生まれの全幕バレエ『パゴダの王子』が、半世紀以上の年月を経て英国と日本を舞台にした二つのバージョンで21世紀にようやく結実したことは、ド・ヴァロア女史が予想した以上の成果と言えるだろう。今後もこの二つの『パゴダの王子』は、現代のフェアリーテール・バレエの傑作として踊り継がれていくに違いない。

東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。