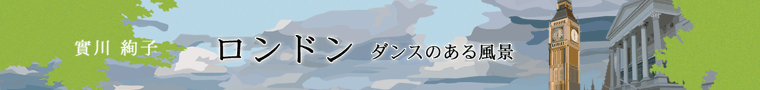Vol.22英国ロイヤルバレエ「メタモルフォシス:ティツィアーノ2012」
ロイヤルバレエ今シーズンの最後の演目は、「メタモルフォシス:ティツィアーノ2012」。10年間芸術監督としてロイヤルバレエを率いてきたモニカ・メイソンが、任期最後を飾る作品に選んだのは、華やかな名場面を集めたガラでも、ロイヤルバレエのダンサーとして活躍した自身の思い出の作品でもなく、〈リスクを恐れず、新しいことに挑戦し続ける〉という姿勢を貫きつづけたメイソン監督の集大成というべき、新作ばかりのトリプル・ビルという非常に大胆な実験的試みとなった。
ロンドン・オリンピックを盛り上げるための文化芸術プログラム、カルチュラル・オリンピアードの一環として行われたこのパフォーマンスでメイソン監督が目指したのは、かつてディアギレフがバレエ・リュスで目指したような、〈総合芸術〉としての新しいバレエだ。
画期的な試みのひとつは、今回の企画がナショナルギャラリーとの合同プロジェクトであるということ。現在公開中のルネサンスの巨匠ティツィアーノによる絵画3点をインスピレーションとした新作バレエ3作品に、同美術館が選んだ今注目の英国人現代アーティストが舞台美術・衣装を担当。ナショナルギャラリーでも同時に、同テーマのもとに制作された彼らの新作アートが展示された。
舞台美術だけでなく、音楽も3人の英国人作曲家に新しい楽曲を依頼。そして、何より周囲をあっと言わせたのが、3作品になんと7人もの振付家が起用されたことである。これだけ多くの才能が一晩のバレエ作品のために一堂に集められるようなことはなかなかない。ルネサンス絵画の傑作が、各界の第一線で活躍する英国人現代アーティストたちに、どのようなインスピレーションを与えるのか――エキサイティングなクロスカルチュラル・プロジェクトに各方面からの注目が集まった。
3作品は、どれも異なるアプローチをとりながらも、モチーフは同じ、オイディウスの叙事詩「変身物語」で語られる神話〈ダイアナとアクテオン〉。女神ダイアナの水浴を目にしてしまった狩人アクテオンが、ダイアナの怒りを買って鹿の姿に変えられてしまい、自身が飼う猟犬に食い殺されるという悲劇である。オリンピックで盛り上がるロンドンで、ギリシャ・ローマ神話を基にした3作品を舞台に上げるというアイデアもタイムリーと言えるだろう。
モニカ・メイソン監督が目指した新しいバレエ、その期待に十分に応えていたのが、最初の作品「マシーナ」だった。振付を担当したのは、ロイヤルバレエのレジデントコレオグラファーであるウェイン・マクレガーと、ゲストのキム・ブランドストラップ。〈ダイアナとアクテオン〉をモチーフにした抽象バレエで、ダイアナの役を演じるのは、なんと高さ5メートル以上もある巨大なロボットの〈腕〉だ。プリンシパル、エドワード・ワトソンが実際に踊る様子をモーションキャプチャでとらえ、数式化してロボットにその動きを与えたという、いかにも科学的アプローチを好むマクレガーらしいアイディアである。巨大なロボットの〈腕〉の先端には、ライトが取り付けられ、その光がダンサーたちを導き、命令し、威嚇する。ティツィアーノの絵画「ダイアナとカリスト」の中で、貞操の誓いを破ったカリストを非難すべく指差しているダイアナの腕を、大胆にも巨大な金属性のロボットの腕として解釈するというアイデアそのものが面白い。
中でもマクレガーによる振付は、人間の持つ情熱を身体を通して剥き出しにすると同時に、その身体に数学的に計算しつくされたかのような人工的・機械的な動きを与え、身体が動くことそのものの意義を考えさせる。ロボットとダンサーたちによるダンスで、一番印象に残ったのが、エドワード・ワトソンとカルロス・アコスタという二人の男性プリンシパルによるデュエット。普段あまり見られない組み合わせだったが、ワトソンの鋭敏で精緻、かつ中性的な踊りと、対照的に力強く男性的なアコスタの踊りは、不思議なくらい調和し、〈ロボット=ダイアナ〉の腕に左右される悲しみと官能性が、理不尽で機械的な力に人間らしい生き方が支配される現在/未来の人間の姿を連想させた。3作品の中で最も抽象的でありながら最もメッセージ性の高い作品に仕上がっていたこの作品によって、モニカ・メイソンが払ったリスクは十分に報われ、新しいバレエの方向性が明確に示されていたといえるだろう。
一方、2作目の「トレスパス」は、「マシーナ」と同じように物語のない抽象バレエでありながら、女神ダイアナは視覚的なイメージとして捉えられ、ティツィアーノの絵画の中でダイアナの額を飾る月のモチーフが、衣装、舞台美術、そして振付の中で繰り返し強調される。この作品で最も目を惹いたのは、舞台中央に鎮座する、月を思わせる半円状の鏡壁。ダイアナが半円の中央で、ブリッジをした状態で宙に向かって放たれた矢のように片足を上に伸ばす等、月をイメージさせるポーズを繰り返しとるのを、透明な壁の向こう側から男性ダンサーたちが凝視する。それはティツィアーノの絵の中でニンフたちの水浴を目撃してしまったアクテオンの視線を再現するかのように、〈見る〉という行為そのものをこの作品のテーマとして浮き彫りにした。そして、女神ダイアナを取り囲むニンフたちが、手でダイアナの目を覆い目隠しをすることで、女性たちが常に〈見られる〉対象であってその反対ではないことが示唆されるのだ。
ウィールドンとマリオットの振付は、彫刻のような静的なポーズが流れるように繋がって、視覚的には神がかった美しさをたたえており、各紙のレビューで3作品の中で最も高い評価を得ていた。
3作目「ダイアナとアクテオン」は、3作品の中で唯一の物語バレエ。ウィル・タケット、リアム・スカーレット、ジョナサン・ワトキンスの若手3人が振付を担当。ニンフたちの群舞をスカーレットが、猟犬たちをワトキンス、狩人たちをタケットがそれぞれ振り付けた。ダイアナとアクテオン役は、マリアネラ・ヌニェスとフェデリコ・ボネッリというこれ以上ないキャスティング。ただし、物語をそのままなぞるような振付はやや助長的で、特にアクテオン役が実際に鹿の気ぐるみのような茶色い衣装に早替わりし、猟犬に食いちぎられて死ぬくだりは、やや文字通りすぎる描写で面白みに欠けた。幕が開くと同時に人々が歓声を漏らした、ターナー賞受賞アーティスト、クリス・オフィリによるカラフルな熱帯雨林を思わせる背景幕は圧倒的な存在感を放っていたが、ギリシャ・ローマ神話を舞台にしたストーリーと振付、そしてオペラ歌手の歌声とはあまり調和しておらず、作品全体としては一番中途半端な結果となってしまったように思う。
全体の印象としては、非常に画期的な試みでありながら、それぞれの世界が確立している多数のアーティスト・振付家を同時に起用し、かつひとつの作品としての調和をはかるというのはやはり難しいのか、それぞれの良さがぶつかりあって作品全体としてやや消化不良的な印象を与えていたことは否定できない。とはいえ、英国バレエ界の、美術界の、音楽界の今後を担う人々を、ひとつの公演のために結集させたそのことは、歴史に残る快挙であることに間違いなく、ロンドン・オリンピックで注目の集まるこの時期に、英国の創造性のショーケース的な作品を作り上げたこと自体がセンセーショナルと言えるだろう。それぞれの作品の課題は次の監督に引き継がれるにしても、その試みを実現するだけの振付家とそれに応えるダンサーたち、さらに新しいバレエを歓迎する観客層をロンドンで育て上げたモニカ・メイソンの功績は十分な賞賛に値する。カーテンコール時に文字通り飛び上がりながら登場したメイソン監督に、劇場中の誰もが心からの拍手を贈った。

東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。