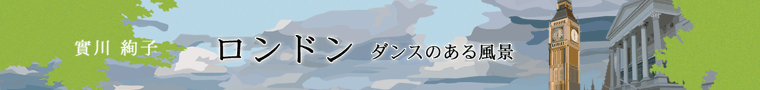Vol.242月15日 英国ロイヤルバレエ団 「マルグリットとアルマン」
〈現実よりもリアルな情熱〉とはマーゴ・フォンティーンが、自伝の中でルドルフ・ヌレエフと踊った「マルグリットとアルマン」のリハーサルを描写した言葉だ。彼らのためにアシュトンが振り付けたこの作品が上演されてからちょうど半世紀後、その奇跡的な情熱が再びロイヤルバレエの舞台に戻ってきた。
アシュトンは、ヌレエフとフォンティーン以外のダンサーがこの役を踊ることは想定していなかったものの、二十一世紀に「マルグリットとアルマン」を踊ったセルゲイ・ポルーニンとタマラ・ロホの二人もまた、スター性・話題性という点では負けてはいない。昨年一月、バレエを辞めると宣言して突然ロイヤルバレエを出ていったポルーニンは、あの騒動から一年して大分落ち着いたと見え、今はロシアに拠点を置いて世界中で活躍しており、今回古巣のロイヤルバレエに堂々ゲストとして戻ってきた。一方、ロイヤルバレエの万能プリンシパルとして長年活躍してきたタマラ・ロホは、昨年夏、イングリッシュ・ナショナルバレエ団の芸術監督に就任したのを機に退団し、今回がロイヤルバレエとの最後の公演となった。

デュマの「椿姫」をもとにした一幕バレエは、上演時間三十分という短さながら、そこには情熱に生きた、元高級娼婦マルグリットと若き貴族アルマンの悲恋が凝縮されている。技術をひけらかすような場面もなく、舞台美術も寝台一台に背景幕があるだけといたってシンプル。さらには大胆にもステップのない〈沈黙〉の時間も多く取り入れられ、台詞はなくとも、二人の間で交わされる視線、些細な身体の動き、そしてこのために作曲されたのではと思うほどドラマティックにストーリーを語るリストの音楽から、二人の愛の物語があざやかにうかびあがっていく。身体という言葉を使って語られる演劇、という言葉がまさにぴったりくる、物語バレエの傑作だ。
短い上演時間の中で、ロホとポルーニンの二人は、一目惚れから始まる真実の愛、愛するがゆえの葛藤、裏切りと別離、再会と許し、そして死へと、マルグリットとアルマンの人生を一気に駈け抜けていった。ポルーニンのぶれのないクリーンなピルエット、滞空時間の長いジャンプ、完璧なラインはすべて健在だったが、なによりバレエファンにとって幸福だったのは、ポルーニンが、これまでの騒動一切を忘れさせてしまうほどに、舞台の上で役を生きることで〈生〉のエネルギーを迸らせているさまを再び目撃できたことだろう。アルマンの激情が、そのままポルーニンのそれと重なり、まさに〈ヌレエフの再来〉と呼ばれるにふさわしい適役だった。

対するロホもまた、それに応えるようにして渾身のパフォーマンスを見せた。時に演技上クールすぎると評されることがこれまでに多々あったロホだが、今回は、マルグリットの心臓が止まる最期のそのときまで、一瞬一瞬彼女の中に熱い血潮が流れていることを感じさせ、焼き尽くすような〈現実よりもリアルな情熱〉があるということを、あざやかに体現して見せた。終幕、死の間際にぎりぎりに駆けつけたアルマンに抱えあげられたマルグリットが、あたかも現世のしがらみに囚われた身体から抜け出そうとするかのように、空虚な宙へと手を差し伸べるシーンのあまりの美しさ、切なさに、会場のあちこちからすすり泣きの声が聞こえてきた。
主演二人のケミストリーこそがすべて、と言えそうなこのバレエにおいて、ロホもポルーニンも、舞台の上でこれ以上ないほどの情熱と輝きを放ち、二人が奇跡的な舞台を実現することが出来る稀有なダンサーであることがあらためて実証された。きっと会場中の誰もがこのペアの踊りをもっと見たいと思ったはずだ。ロイヤルバレエではこれが最後になると思うと、本当に残念でならない。


東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。