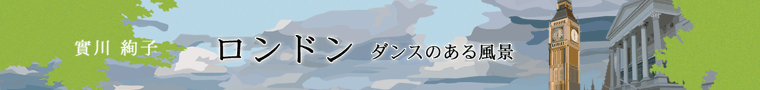Vol.285月11日 英国ロイヤルバレエ団『ウルフ・ワークス』
2月のある日、ロイヤルバレエ団の新しいスターであるナタリア・オシーポワとマシュー・ゴールディングの鮮烈な『オネーギン』デビューの夜、帰り道にアレッサンドラ・フェリを見かけた。小柄で華奢な体躯、くるくると表情を変える好奇心の固まりのような大きな瞳は、90年代に何度と観たマクミラン版『ロミオとジュリエット』の中のフェリそのままでありながら不思議な憂いをたたえており、大勢の人が行き交う中で、小さなフェリの身体の周りだけが不思議な暈光に包まれているかのようだった。あのアレッサンドラ・フェリがロンドンにいる。2007年に一度現役を引退したフェリが、古巣ロイヤルバレエにまた、戻って来たのだ。

脳科学、近未来テクノロジーといった知的なテーマと、常にアグレッシブに限界に挑むような新しい身体性の追求を融合させることで知られる現代バレエの鬼才ウェイン・マクレガーが、20世紀初頭の英国を代表するモダニズム作家ヴァージニア・ウルフをモチーフにした初の全幕作品を制作中であり、しかもかつてのドラマティック・バレリーナの代名詞であるフェリが主演すると聞いた時は、あまりにも意外な組み合わせだったために、にわかに信じがたかった。2006年からロイヤルバレエの常任振付家を務めるマクレガーだが、『レイヴン・ガール』をはじめ、ここ最近の作品は不評続きだったこともあり、初の全幕作品での失敗は絶対に許されないというプレッシャーは相当なものだったはずだ。その中で、得意とする現代的な抽象バレエから一歩踏み出し、初めて英国文学作品を題材に選んだことは、ある意味大きな賭けだったに違いない。かつてのマクミランのミューズであったフェリを主演にすえ、マクレガーの従来の手法の対極にある英国バレエの伝統の物語バレエにあえて挑戦し、そこで新たな表現を模索しようというその意気込みに、公演前からバレエ界内外の期待が高まっていた。
『ウルフ・ワークス』は、3幕からなる全幕作品だが、1幕が『ダロウェイ夫人』、2幕が『オーランドー』、3幕が『波』というウルフの三つの代表作からインスピレーションを得たものとなっており、それぞれが独立した作品のようでありながら、同時に全幕を通して共通のトーンをたたえている。〈意識の流れ〉という独自の文学形式を確立したウルフの作品は、時系列に従って表面的な物語が進行していくのではなく、登場人物の内面世界に焦点を当て、時間も空間も超えて、意識が流れるままに語られていく。これは改めて考えてみれば、言葉を持たないダンスの特性と重なる部分でもあること考えると、なぜ今までウルフ作品がバレエ化されなかったかということの方が不思議なのかもしれない。
1幕の「I now, I then」は、ヴァージニア・ウルフの肉声が、言葉と創作について語る所から始まる。“Words, English words, are full of echoes, of memories, of associations—”という一節で始まるウルフの朗読とともに、 52歳のフェリが、現在の老いたクラリッサ・ダロウェイとしてたたずんでいる。舞台上に浮かぶ、思い出を縁取るフォトフレームのような大きな枠の間を流れるように走り抜けるフェリは、かつて求愛されたロマンチックなピーター・ウォルシュでなく、堅実な夫リチャード・ダロウェイを選んだことが正しかったのかどうか、若き日の自分を回想しながら自問し、現在と過去が錯綜していく。いつのまにか若かりし日のクラリッサと親友サリーの戯れの中に入っていく現在のクラリッサが、サリーに思わずキスをする場面は、これが彼女の人生の中で最も輝ける時だったことを象徴する切なさに満ちた場面であった。

ピーター、リチャード、戦争後遺症に苛まされるセプティマスなど、それぞれのキャラクターの感情と記憶が、マクレガーには珍しいクラシックのステップで視覚化されていくさま、そしてフェリがただ舞台に佇んでいるだけで、そこに物語を生み出してしまう存在感にただただ圧倒された。時系列の物語はなくとも、リアルな感情表現と鮮明なキャラクター描写が、胸に迫る新しい物語バレエの形を可能にしたのだった。また、〈記憶〉という主題は、若干19歳でマクミランに見いだされ、ここロンドンのオペラハウスからプロダンサーとしての人生を切り開いていったフェリ自身の人生の記憶とも重なって、更なる深みが加わったことも否定できない。
一方、一人一人のキャラクターの感情のひだを巧みに描くことに成功した1幕に比べると、2幕「Becomings」は少し残念な結果となった。エリザベス一世が統治する時代に生まれた貴族オーランドーが、いつの間にか女性となり、時空を超えて活躍する物語であるが、男性ダンサーが着ていた、エリザベス朝風の襟がついた両性具有的な衣装や、鋭いレーザー光線が舞台を遮る中で踊るダンサーたちの高速の動きは見応えがあり、今やロイヤルのスターであるナタリア・オシーポワの目を見張るような180度以上の開脚が高速で繰り返されるさまも圧巻であったが、暗い舞台上でキャラクターの差異や内面がなかなか伝わってこなかったのが惜しかった。

3幕「Tuesdays」には再びフェリが、今度はヴァージニア・ウルフ本人の役として舞台に舞い戻った。波の映像をバックに、ウーズ川に入水自殺する前に書かれた夫宛の手紙が朗読される。「私たち以上に幸せな二人はなかったでしょう、この恐ろしい病気が始まるまでは・・・」という一節が、1幕のクラリッサの苦悩とも重なり合い胸に迫る。ロイヤルバレエ学校の生徒たちや、コールドバレエが、フェリを取り囲むようにして波の動きを表現する場面はやや助長的だったが、1幕で目指され、2幕で中断していた意識の流れのバレエが、再び具現化され、最後に静かに波にのみ込まれていったフェリの姿に、観客の多くが涙した。

技術にずば抜け、若さ溢れるロイヤルバレエのダンサーたちの中にあって、圧倒的な叙情表現でもって人間の儚さ、繊細さを立ち姿だけで表現したフェリ。演劇の国英国ロイヤルバレエの伝統は元々、ダンサー一人一人が、〈キャラクター〉を演じられるパフォーマーであることであったが、これこそ今のロイヤルバレエに欠けているものではないかと、フェリを観て改めて感じた夜だった。

東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。