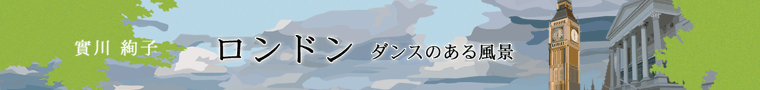Vol.296月19日 イングリッシュ・ナショナル・バレエ団『コレオグラフィクス』
ダンス界の発展に欠かせないものの一つ、それは振付家の育成だろう。『コレオグラフィクス』は、イングリッシュ・ナショナル・バレエ団が主催する、新進の振付家のための実験的ショーケースともいえる毎年恒例のイベントだ。今年は同バレエ団のダンサーが四名、外部の振付家二名が参加し、英国を代表する振付家ラッセル・マリファントのワークショップで研鑽を積んだのち、サドラーズウェルズ劇場併設のリリアン・ベイリス・スタジオ小劇場にて、それぞれの作品を発表した。
今年のテーマは、〈戦後アメリカ〉。興味深いことに六つの小作品全てが、男女間のリレーションシップをめぐるドラマ、特に再会と別離にまつわる作品になった。中でも日本のバレエ団での客演も多い同団のソリスト、ジェームズ・ストリーターによる『ア・タッチ・フォー・エタニティ』と、アーティストのスティーナ・クイージュブールによる『ア・ルーム・イン・ニューヨーク』が特に目を引いた。
両作品に共通しているのは、ともに戦後アメリカを生きた実在の夫婦の物語にインスピレーションを得ていることだ。『ア・タッチ・フォー・エタニティ』は、戦後、スパイ罪で有罪判決となり同日に処刑されたローゼンバーグ夫妻の、処刑直前の最後の会話に基づいた作品。前半部においては、二人のダンサー(アデラ・ラミレズとホアン・ロドリゲス)が、別々に照らし出された独房の中で円を描くように流動的な動きを繰り返しては、求心力に引き寄せられるようにして近づいては離れ、文字通り哀しい運命をともにすることになった悲劇の夫婦像を鮮やかに描き出してみせた。ユニゾンでの踊りにはタイミングに問題が見受けられた場面もあったが、処刑直前にやっと敷居越しに同じ部屋に入ることが許され、最後の接触を果たした決定的な瞬間を境に、ドラマティックなパ・ド・ドゥが展開していく。オフバランスのリフトや、ラミレズの乱暴なまでに高く投げ出される足が、迫りくる死への絶望と、痛々しいまでの刹那をよく体現していたように思う。

ストリーターの作品が、回避不可能な死を目前にした最後の生の瞬間をモチーフとしているならば、クイージュブールの作品で描かれているのは、その対極にある、不幸な夫婦生活の中で徐々に進行する魂の死である。作品は、画家のエドワード・ホッパーの妻、ジョセフィーンの日記をもとに、水と油ほどに異なる気性を持った二人のすれ違いを描く。前半部では、息もつかせぬ速度で暴力的なまでに荒々しいリフトや回転が繰り返され、二人の呼吸を荒げるような激しい衝突が休みなしに続き、後半部では一転、ともに生活をしながら理解し合えない夫婦の静かな哀しみと乾いた孤独が、ひたひたと舞台空間を満たしていった。お互いの口を押さえて相手の言葉を塞いだり、アイコンタクトを避けて踊る場面は、ホッパーによる絵画『ニューヨークの部屋』(1932年)や、『ナイトホークス』(1942年)の中で描かれる、同じ空間を共有しながらどこまでも孤独な、都市に生きる人々の姿と呼応するものだ。燃えさかる炎のように激しいジョセフィーンの気性と彼女の哀しみを丁寧に描き出したクイージュブールの作品を見て、生身の女性が持つさまざまな様相を繊細に描き出せる彼女のような女性振付家こそ、男性振付家が圧倒的多数を占める今のダンス界が必要としているものなのではないかと感じた。

意図的ではないとはいえ、異なる舞踊言語を用いて実存した夫婦を描いた二作品を対比しながら鑑賞することができた『コレオグラフィクス』は、非常に示唆に富んだ公演となった。その他の四作品もまた、戦争による男女の別離や死を描いた短くも重厚な作品が多く、六作品立て続けに見たあとでは少しテーマに偏りがありすぎた印象が残ったものの、積極的に若手ダンサーに創作の機会を与えるこのような公演は、若手振付家の育成と将来のレパートリーの充実のためにあらゆるダンスカンパニーがモデルとすべき事例であるといえるだろう。

東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。