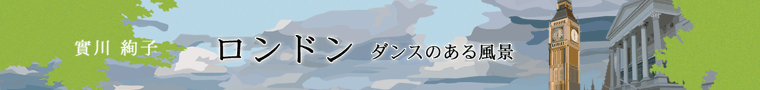Vol.30●7月10日 オランダ国立バレエ団『シンデレラ』
アシュトン、ビントリーに続き、若手イギリス人振付家クリストファー・ウィールドンが振り付けた最新の『シンデレラ』(2012年、アムステルダムで初演)のロンドン初演を鑑賞した。
ウィールドンの『シンデレラ』には、魔法使いも、カボチャの馬車も、ガラスの靴も登場しない。ダークなグリム兄弟によるバージョンをもとにしたというウィールドン版は、砂糖菓子のように甘いおとぎ話ではなく、一人一人の人間的な魅力を生き生きと描き出すドラマとしての新しい『シンデレラ』である。
鳥がさえずる森の中で、シンデレラが両親と仲睦まじく佇んでいると、突然母親が血を吐いて倒れるという幕開きはとてもショッキングだ。シンデレラの数奇な運命を象徴するかのように、プロコイエフによる重々しい序曲が始まり、黄金のマスクを付けた四人の「運命」が現れる。彼らの存在は観客以外に見えず、黒子のような役回りでほぼ全場面に出演し、シンデレラを文字通りサポートし、彼女の人生を導いていく。
魔法使いの代わりに、不思議な力でシンデレラを変身させるのは、大きな木だ。幼いシンデレラの涙が母親の墓に降りかかると、そこから芽吹いてぐんぐんと大きな木が出現するシーンは圧巻。母なる木が、母親の代わりにシンデレラを愛で包み込む。
キャラクターの描き方もユニークでリアリティがある。母を失ったシンデレラのもとに父親が新しい家族を連れてくる場面では、シンデレラは彼らから差し出される花束を拒絶し、運命をただ受け入れるのではなく、運命を自ら切り開いていくモダンな女性であることが強調される。また、別のバージョンでは内面が殆ど描かれない王子のキャラクターも、幼少期にまでさかのぼって掘り下げている点が面白い。友人ベンジャミンと共に悪さをするやんちゃな幼い王子は、成長してもその天真爛漫さはそのままに、両親の言いつけ通りに政略結婚しなければならない自分の人生に疑問を感じている。
そんな二人は、舞踏会の前に出会う。ロッシーニのオペラ版『シンデレラ』に基づき、乞食姿に変装した王子と、王子に扮した親友ベンジャミンがシンデレラの家に舞踏会への招待状を持って現れるという設定で、義母や義姉たちが偽の王子ベンジャミンに媚びへつらうのに対して、シンデレラだけがみすぼらしい姿の王子を丁寧にもてなす。アシュトン版でシンデレラが帚と踊る有名な場面は、乞食姿の王子がシンデレラにダンスを教えるほほえましい場面になっており、二人の幼少期と苦悩が丁寧に描かれたことで、この二人が出会うべくして出会い、階級や見た目ではなく、人間として惹かれ合ったのだということが十分に伝わってきた。
アシュトン版で男性が演じる義姉たちは、女性によって演じられる。一人は見た目は美しいが、中身は最低、弱い者いじめをして常に自分に注目が集まらないと気が済まないエドウィーナ。もう一人は、特に美人ではないが、心は優しいクレメンティーン。以前は彼女がシンデレラの代わりにいじめられていたこともあって、シンデレラには同情しながらも、姉に言われて嫌々いじめに参加している、という現実味ある設定だ。そしてそんなかわいそうなクレメンティーンにも、シンデレラとは別のハッピーエンディングが用意されているところが心憎い。
クリストファー・ウィールドンが英国ロイヤル・バレエ団に振り付けた『不思議の国のアリス』や『冬物語』では舞台美術が評判になったが、彼の才能の一つは、デザイナー選びのセンスの良さにあるようだ。『シンデレラ』でタッグを組んだのは、昨年ミュージカル『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』の舞台美術でトニー賞にもノミネートされた、ジュリアン・クラウチ。甘すぎずスタイリッシュなシンデレラのドレスや、花火を鑑賞しにテラスに出た舞踏会の招待客がシルエットとなって浮かび上がる場面など、洗練されたセンスが光る。また、シンデレラを見守る母なる木と、そしてその枝が馬車に変身するまさに魔法のように魅惑的なシーンは、人形遣いのバジル・ツイストが担当。生きた絵本が目の前で展開していくようなスペクタクルに思わず息をのんだ。
ウィールドンの振付は、どこまでも流れるような動きが、まるで物語のページをめくるようにしてシームレスに展開していくさまが見事で、特に「運命」たちがシンデレラをリフトしてダイナミックなイメージを展開するさまには思わず目を見張った。シンデレラ役のプリンシパル、アンナ・ツィガンコーワは、プリンセスになるのを待っているかわいらしいシンデレラというよりも、自らが何を求めているかをはっきりと知っているクールで知的なシンデレラ。私生活でのパートナーであり、今は英国ロイヤル・バレエ団のプリンシパルとなったマシュー・ゴールディングと共に踊るツィガンコーワは、シンデレラのキャラクターと重なって一際輝きを放っていた。
母なる大地を象徴するような大きな木の下での結婚式は感動的。どんな世代でも楽しめるような、総合芸術としての醍醐味を味わわせてくれる作品に仕上がっている。

東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。