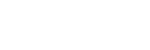|
|||||
|
|||||
| 先日、昼間に日本舞踊を見て少し疲れていたのですが頑張ってオーチャード・ホールでの「グランディーバ バレエ団」の初日の舞台に行って来ました。もう御存知とは思いますがド派手な化粧・衣装で女装したりして大袈裟な動きで笑わせる男性ばかりのバレエ団のことです。 もう20年以上も前、ニューヨークから「トロカデロ・デ・モンテカルロ・バレエ団」が初来日して、バレエ芸術を神聖視している日本の観客を驚倒させました。「芸術か冗談か」というキャッチコピーでしたが、やっぱり冗談のほうでした。「白鳥の湖」第2幕のパロディ等々面白くはありましたがお上品でもお上手でもないものでしたが、そこが面白くて強く印象に残る舞台でした。 当時僕はまだNHKにいてクラシック音楽を中心にオペラやバレエなどの番組を作っていたのですが、まさかNHKで放送しようという考えはありませんでした。ところが僕たちの部でなく劇場中継の部の女性ディレクターがこの公演を収録して放送したのです。女性陣の中には革命的なことを実現してしまう勇気のある人もいるんです。上司たちの無関心や無知を利用しての快挙ではありました。初来日公演は大成功で以来たびたびの来日で確実にファンをふやしました。バレエとは芸術でなければならぬという常識が崩れかけていた時代だったのでしょうか。 そのうちにこのバレエ団を脱退した人々が同じようなバレエ団を作りました。これが「グランディーバ バレエ団」です。このバレエ団も1997年の初来日以来、人気を爆発させ、毎年のように来日しています。日本テレビの「とんねるずの生でダラダラ...」とかいう番組をはじめ多くのテレビに出演するなど、マスコミを巧妙に利用しての宣伝も効果をあげています。2つの珍バレエ団は日本を最大の市場として、日本でしのぎをけずっているのが現状といえましょう。 今回の「グランディーバ」(偉大なる女神!)はすごく成長して、もうただのキワ物ではなくなっていました。ところが満員の客席には顔なじみの舞踊家や批評家のかたがたの姿は見られず、あまり舞踊とは関係のないような女性陣が大喜びで舞台に見入り、時には手拍子をたたいていたのはいつものとおりです。 専門家を見かけなかったのは、出演者にお目あてがいなかったり、コミック・バレエは批評の対象にはならないと考えてもいるからでしょう。男性だけの妖しげなバレエは気持ち悪いというかたもいるでしょうが、この舞台は一見の価値はありました。 考えてみますと、われわれ日本人には芸術として認知されている立派なものばかりを尊重するエリートと、芸術を敬遠してとにかく娯楽を楽しもうという愉快派とに大別されてしまうようです。現実にクラシックオタクの友人はバレエを軽視していますし、逆にバレーは見るけどバレエに近づきにくいという友人もいます。バレエブームといってもそんなものともいえます。こういった両極端の人々にもこういうおかしなバレエを見て欲しいような気もしました。どうせ一回しかない人生です。芸術に感動し、娯楽をエンジョイするという欲張った人生のほうが、少なくとも気持ちだけはリッチになりましょう。 そして今回見た舞台は娯楽に徹していながらも本物のクラシックバレエより緻密に出来ているものもあり、男性ながらトウシューズの技術も立派でした。彼(女?)らは立派なプロ意識の持ち主になっていたのです。 ロックのコンサートで売られているような大型の派手派手しいプログラムを見ると、今回は5月の初めから8月8日まで全部で60回近い公演が続くようです。これは外来のメジャーなバレエ団の公演回数をも上回るかと思います。それだけチケットが売れるんでしょうね。プログラムには女装した男たち各人が微笑んでポーズしている左上には素顔の男っぽい姿があって変身の楽しさ凄さを伝えています。彼らの芸名はふざけたものが多く、芸術監督兼ダンサーのヴィクター・トレヴィノはニーナ・ミニマキシモーヴァという名で、ロシアの名花の名前を遠慮がちにチャッカリと引用しています。他にもダーシー・マッセルはロイヤル・バレエのダーシー・バッセルをもじり、ナタリア・マカブラはもちろんマカロワをちょっと不吉な名に変えています。等々憧れのバレリーナの名前を厚かましく拝借している人も数人いるのも愉快です。 今回の日本公演ではだいぶメンバーチェンジがあったらしいのですが、21人全員が女になったり男に戻ったりと42人分の名前が並んでいたわけですが、そこはバレエのこと、憧れの女性しか踊らない人もいるようです。 皆さんの中にはもう舞台をごらんになったかたも少なくないとは思いますが、見ていない人や少しは興味のある人のために初日の舞台の様子を御報告しましょう。 初日の公演は「開会式」という副題がついていて、定番の「白鳥の湖」第2幕などを避けて、新作の発表を兼ねていたようです。 全体は3部から成り、第1部は新作「ワルプルギスの夜」です。これは日本でも50年以上も前にボリショイ・バレエの初来日の時に上演されて以来われわれにもおなじみの舞台ですが、それをさらに過激にしたものです。グノー作曲のオペラ「ファウスト」のバレエシーンとして作られたのですが、現在では独立して上演されています。一年に一晩だけ、ブロッケンの山に魔物たちが集まって騒ぐ様子を描いているので、このバレエ団にはピッタリの作品でしょうが、僕の見る限りではもっといやらしくしたほうがよかったとも思います。 第2部は小品3つ。まず「太っタンゴ」。衣装につめ物をして精一杯太った中年風の男女がピアソラのタンゴに乗っての重量感のあるダンス。ついで「ハーレキナード・パ・ド・ドゥ」は可憐?な少女(黒人のテクニシャン、エリー・スパーカー)と道化役(背の高いムラデノフ)のグラン・パ・ド・ドゥ。女性役の超人的な技術と女性にはできないオーバーな表現は作品の面白さを拡大していました。「ドン・キホーテ パ・ド・ドゥ」はアダージョとコーダを技巧派のデブロコーヴァと巨漢オスワルド・マニュース組、男性のヴァリエーションは日本人の瀬川哲司、女性ヴァリーションも別の人というキャスト。女性役をサポート中の男性は客席に向かってニコッと笑いかけて自己顕示を見せたり、コーダでは女性役が注目のグラン・フェッテの最後に倒れてしまい(ワザと?)床をたたいてくやしがったりするなどダンスとドラマを両立させました。古典バレエの19世紀的なのんびりした時間をあえて忙しくて飽きさせない工夫をしているのです。これなど一般のバレエ公演では見られないことでしょう。 第3部はまず名作「バラの精」。フォーキンの原作の構成・振付を守りながらも巨人の少女役と小柄なバラの精がコミカルな演技を散りばめて、この作品の裏から光を当てて見せました。つづいて十八番の「瀕死の白鳥」。今回はティファニー・アン・カルティエというブランド風な芸名の細長いダンサーが鳥のような手の動きを強調して大喝采を受けました。くりかえされる幕前での答礼中に、幕の内からスタッフの手で早くひっこめという合図があっても、そしらぬ顔でおじぎを続けながら左手でさらなる拍手をけしかけて爆笑を誘うなど細かく計算された演出です。何となくプリセツカヤの濃厚なレヴェランス(おじぎ)を思い出してしまいました。 フィナーレも新作「トゥッティ・フルッティ」は果物だらけという意味でしょうか。南国的な果物が並びます。女たちが大きなバナナを一本ずつ振りかざすのも少々イミシンに見えてしまいます。パリの深夜の名物ショーをもう少し下品にして面白おかしくしたような感じです。バレエというよりはショー的な楽しさを満喫しました。ということでめでたく幕がおりて、昼間の疲れもふっとんで元気に家路につくことができたのです。 とにかくこのバレエ団は成長していました。ニューヨーク・シティ・バレエでバランシンの信用が厚かったポール・ボーズがバレエ・マスターをしているなど、技術的な基礎がしっかりしていて、その上に各人各様の味つけをしているので、古くさい作品も再確認させてくれたりもします。 男が女に化けるなんて気持ワルーイというのは簡単ですが、日本には男だけの歌舞伎や能があるじゃないですか。既成のバレエファンとは別の人々も多い観客たちの自発的な手拍子が舞台を盛り上げたりと、ポップス的な広がりも感じました。いろいろ考えさせ見させてくれる舞台といえましょう。 日本では悲劇的なもののほうが芸術的で、喜劇的なものは下に見られる傾向がありました。能と狂言もそう。しかし両者は本来お互いに引き立て合うものです。喜劇的なものは作るのも演じるのも至難で、観客の目も厳しいようです。近ごろ流行しているお笑いのコンテストをテレビで見たりしますと、ネタの面白さ、対話のタイミングのよさなど、本当に大変な仕事だと感心してしまいます。 今回の「グランディーバ」の舞台でいろいろ考えさせられてしまったのですが、この舞台、理屈抜きで楽しむことがまず先決かも知れません。人生にはバカバカしい楽しみも必要だと痛感している昨今です。 |
|||||
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.