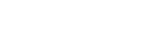|
|||||
|
|||||
| [Ballet]を日本語に訳すと[舞踊劇]これは舞踊家にとって衆知の事であるが、前回の「白鳥の湖」「シェラザード」等古典作品は、劇的構成においては非常にシンプルと云うべきか非人間的物語である。観客の心の中に踏み込んで赤裸々に心の流れを追う心理的バレエといえば私は古典作品では「ジゼル」を。又心理的バレエの発祥と云える名将アンソニー・チューダ氏の「ライラック・ガーデン」(日本名リラの園)を上げたい。この2作品について二人の舞踊家との出会いについて語りたい。 チューダ氏に初めてお目にかかったのは、太刀川瑠璃子氏のスターダンサーズ・バレエ団結成公演の時であった。実は太刀川さんから「リラの園」の婚約者の役の出演交渉を受けたのだが、当時振付者としてスタートしたばかりの私は、躍手として舞台出演する事は振付者としてのみの成長を目指す自己の信条に反するとお断り致しました。しかし、出来ればチューダの振付の現場と作品の仕上げ等研修させて下さいとお願いしました。許可を受け何回かリハーサルを見学するうち彼と親しくなり、彼が横井の作品を見たいと云い出しました。当時私の小さな東京バレエグループは秋にしか公演活動を行って居りません、と申し上げるとTV作品でもよいとの事なので作品を見て頂く事に成りました。 作品は作曲家の三善晃氏がNHKラジオの依頼を受け、イタリア放送音楽コンクールに出品されて見事グランプリを受賞された「オンデーヌ」を以前NHKTVで振付映像化したものでした。オンデーヌ=木村百合子、騎士ハンス=江川明の配役で、モダンダンサーの百合子と演技派バレエダンサー明の二人の組み合わせが良く生かされた自信作でありました。NHKのスタジオで作品を観て頂いた後、江川を交えて喫茶店で感想を伺いました。 彼は「今回の私の出演者以外にこれほどの演技者が日本に存在していたのは素晴らしい事だが、私の作品に出演していない事がとても残念です、大変東洋的思考から創られた良い作品でした」と語られました。「ビールを飲みたい」と云われたチューダと私は通訳をお願いした星野安子さんと三人で六本木のニコラスと云うピザ屋に向かいました。世界的巨大な振付者と音楽について、文学について、美術について、そしてバレエの作品に、振付法と次々に話は絶えませんでした。事毎に話しの合った二人でしたが意見が異なったのは美術についての事でした。チューダが愛したのはロートレック、モネ、シャガール等美しい印象派の画家たちで、私が自己の世界の反映とも思っているサルバルドール・ダリについて「どうしてあのようなグロテスクな絵が好きなのか理解出来ない」、私は「そこにこそ互いに育った時代の差異が有るのではないか」と今から考えれば大変生意気な返事をしました。通訳の星野さんは辞書を繰りながら「なんでこんな難しい話しばかりなの」とブツブツ、こうして初めてお目にかかった本物の振付者から様々な舞踊に関するレクチャーを何と6時間にわたりお受けする事が出来ました。時財布を手にするチューダに「今日は私の招待、日本では私が支払うのがしきたりです」そしてチューダを赤坂プリンスに送り届けた時「日本人は富士山と天気の事しか話題がないが、本当は今夜のような話がしたかった、おかげで明日が公演初日であるのを忘れる事が出来ました有り難う」と云われると、私の上着のポケットに何かを差し込んでホテルの中に消えていきました。ポケットに手を入れるとお金が入っているのでした。あわてる私に星野さんは「しかたないわ、まるで大学教授と大学院生の授業のようだったのだから」と云われました。 はじめて観たスターダンサーズ・バレエ団の「リラの園」はショーソンの甘美な音楽に乗り、全ての踊手の登場と退場が作品のスリリングな演出に生かされ、演技者の繰り広げるそれぞれの役の心理的葛藤を表現し、ドラマの流れを観客に完全に伝える事が出来た素晴らしい作品であり、チューダの一番の名作と今でも想い出すことが出来ます。 1968年文化庁芸術家海外派遣研究員としてNYに行った時、故市川雅氏と共にジュリアード音楽大学に彼を訪ねました。すると全て市川市の通訳を通す私に「何故横井は英語で話さないのか、東京ではあんなに話したのに」と、多分前回のレクチャーの内容を覚えておられたのでしょう。そして「君はNYに遊びに来たのでなく研修に来たのである、明日からジュリアードの室を貸してあげる、作品を創りなさい」と再会を喜んで下さいました。 次の日ジュリアードの教室の一つに[Mr YOKOI ]の名札が付きました。 次に古典作品「ジゼル」に話しを変えようと思います。20代前半現役ダンサーとしての私は小牧バレエ団脱退組による「東京バレエ協会」と名乗るバレエ団の結成に参加しました。旧帝国劇場での旗揚げ公演に「ジゼル」他の上演を行ない、其の後大阪を初め九州中国等連続30回のツアーを持ちました。配役はジゼル=広瀬佐紀子、笹本公江、アルブレヒト=横井茂、バチルド姫=日高淳、ヒラリオン=永江厳、であり皆20才代の若々しい舞台であったと思います。私にとり初めての主役であり緊張しながら作品の稽古に励む日々、ある映画会社の御厚意でジゼルのフイルムを見せて頂く事が出来ました。モノクロームの映画でありましたがアントン・ドリーンのアルブレヒトの演技を繰り返し上演して頂きながらメモを取り大きな勉強の一時を持つ事が出来ました。私の演技はさておき、公演自体は大成功に終わりましたが、私の中に解決出来ない一つの疑問が残りました。それはアルブレヒトの従者ウイルフリードの存在でした。第一幕の冒頭アルブレヒトと共に登場し何かアルブレヒトを諌めるようなマイムの後、退場を命じられるシーン。バチルド姫の登場を知らせに慌ただしく登場するシーン。一幕の終わりでのシーン。二幕終わりでアルブレヒトを捜しに来るシーン等このウイルフリードは何者?劇設定の中に於ける位置は?考えれば考える程解らなくなりました。これほどジゼルの揺れ動く心理を追った、これだけ緻密な劇的構成の中で単なる従者の存在であるはずが無い、この疑問の解決は20年後にやって来ました。1969年文化庁研修員の旅の時サマーフェスティバルの研修のため立ち寄ったレーニングランド(現在の・セント・ペテルスブルグ)のキーロフ劇場の「ジゼル」を観た時でした。ジゼル役のコルバコワの演技の素晴らしさはさておき、問題のウイルリードの演出上のあつかいに初めて私は納得する事が出来ました。次の日ワガノワ振付者学校にこのジゼルの演出者であるドジンスカヤ女史を訪問し、色々お話を聞く事が出来ました。(ロシア語の完全に出来ない私が何故と思われると思いますが、実はレーニングラードに着いたとたんに、私には元日本人を名乗る男性がピタリとくっついて居ました。スパイと思われて秘密警察の係官が監視の為何時も側に居たのです、しかし私にとっては金銭的に只の通訳として大変便利なことでした)そして昨日のジゼルのウイルフリードのあつかいについてとても良く理解が出来た話しをすると、彼女は次の様に話し始めました「よく見て下さいました、私もウイルフリードのあつかいに対して永い間疑問を持っていたので今回の上演には彼の役に一つのテーマを持たせたのです。通常は傍観者としてのウイルフリードに実は主人公アルブレヒトの心の奥にある良心を反映させ、アルブレヒトの王子の身分、村人ロイスとジゼルの恋人との身分の狭間を浮き彫りにしたかったのです、アルブレヒトの愛は嘘ではなく真実であったと告げたかったのです」と語られました。 これら2作品のような心理的な作品は現在の作品創造にはほとんど見る事が出来ないのは大変に残念な流れである。次々と生産されて続けているコンテンポラリーダンス等は動きの面白さのみを追いかけ芸術の本当の姿である魂からの叫びを伝える媒体としての舞踊を忘れさられているように私は感じる。流行にのった形ばかりの美しさ面白さは芸術ではない、つましくても幼くても心からの言葉に満たされた舞踊を私は観たいと思う。 あれから30年余、私は観客の心を動かし興奮させる心理的バレエを創り続けたいと今も念じている。 |
|||||
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.