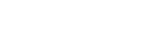|
|||||
|
|||||
| 昨年12月時間をつくってヨーロッパに旅をした。わずか一週間であったが幸いパリ在住の姪が全て手配をしてくれたので、ついた次の日から毎晩劇場に通う事が出来た。12月1日と2日は、Opera
Bastille でオペラ、リヒャルト・ワグナー曲「さまよえるオランダ人」オペレッタ、ヨハン・シュトラウス曲「こうもり」の作品であった。オペラの大好きな私は今までオペラの仕事を断ったことはない、そのオペラの中で一番多く振付・演技指導を行ったのがRICHAROWAGNERの作品群であった。 大阪万国博覧会の「ライン・ゴールド」の黄金を守る人魚達の舞台表現を行った6人の踊手たち、山田奈々子、加藤よう子、新井雅子、竹屋啓子、田中りえ、亀ヶ谷環、の振付にはじまり、この「ライン・ゴールド」は数十年に渡り3回も上演に参加した。又、同じ作曲家の「タンフオイザー」の振付に至っては別々の公演にやはり数十年に渡りかかわる事となった。内垣啓一、鈴木啓介、西沢敏一、そして再び西沢敏一等この三人の演出家との共同作業は、大変難しくあったがそれなりに楽しく名誉な仕事であった、多分日本国内で上演された全てのタンフォイザーに私は関与したのであろう。 しかし、舞踊シーンの全く無い「さまよえるオランダ人」は、いつも客席で観ていた。はじめての出逢は日生劇場の柿落し公演であった。オランダ人の登場を知らせるように、舞台奥に巨大な赤い帆が現れた時の強い迫力を忘れる事は出来ない。その後色々な演出を何回か観る機会はあったが今回のオランダ人はまったく異なった作品に仕上がって居た。開幕すると舞台全体は中央で大きく二つに分割され、上手部分は白い壁に埋められており、壁の奥よりに巨大な高さ人の五倍もあるやはり同じ白い扉がある。下手は褐色の壁で中央に、荒れ狂う波に満たされた海の絵画が見える。劇が進行しやがて上手の扉が少し開き一人の男の影が大きく映し出されるオランダ人の登場である。全体的に音楽と演出と照明が一体化し良い効果を出して居た。終幕主人公ゼンタが死ぬと上手の扉は閉まり、かわって下手の絵画の中の荒れ狂う波は静まり大きな白い帆を張った帆船が現れ海は浄化されて行く。ワグナーの台本の物語性よりも主演者たちの心の流れを追った心理劇と感じられ、大変素晴らしい演出であった。 次の日はJOHANN STRAUSS「こうもり」であった。このオペレッタは音楽フアンにとり一番なじみ深い作品であり、私も日本オペレッタ協会の依頼により寺崎裕則の演出により北トピア大ホール、新国立劇場大ホール等の公演に参加して来た。ことに昨年10月北トピア大ホールにてRudolf Biblの指揮で行われた公演に「青きドナウ」のバレエを振付けたばかりでありとても興味をひいた公演であった。このオペレッタのあらすじは、中年夫婦の恋愛遊びを新年を迎える大晦日の晩の盛大なパーティーのシャンペンの香りの様に、演出方法によってはかなりエロチックな大人の夢物語である。しかし今回の「こうもり」の序曲途中からの開幕には驚いた、舞台空間の上からゴム紐につるさわれた縦じまの囚人服の蝙蝠男が舞い降りて来た。彼の演技はまさにオリンピックのつり輪そのもので、様々な難しい動きをえんえんと続け、序曲の終わり頃にはこの蝙蝠は数十人となった、まさにあの美しいシュトラウスの音楽は吹き飛んでしまった。フランス語のスペクタルはたしかに「見せ物」の意ではあるが私は大きな疑問を感じた、本来このオペレッタに登場する「蝙蝠博士」が主人公アイゼンシュタインに対する復習のため色々の筋書きをはこんで行く物語であり、蝙蝠について云えば作品之主題とは関係ない、蝙蝠でなくとも他の生き物でも良かったのである。舞台美術は壮大と云える位大掛かりでそれなりに納得出来たがシュトラウスの音楽を感じる事が出来たのは、第三幕ラストの「蝙蝠ワルツを」踊るコーラス達のきわめて正確なワルツステップであった。既成の作品に対する演出の切り込み角度は様々な方法があるが、ウイーン大好き、シュトラウス大々好きの私にとっては真実今すぐ歯を洗いたくなる食べ物を口にしてしまった様な感じであった。アンコールの途中から外に出た私はタクシー飛び乗り北に向かった、目指すはモンマルトルの丘であった。36年まえ文化庁芸術家在外研修員一期生として1969年NYからパリー入りをした直後街は学生運動の渦にのみ込まれ、オペラ座をはじめルーブル美術館はクローズ、はては地下鉄まで止まり銀行も閉まってしまいました、世にいう5月革命の中に入ってしまったのです。ほうほうの体でパリーからブリュセルに移動して研修を続けた私にとりキャバレー・ムーランルージュは一度は訪れたい場所であった。11時からのシヨータイムは絢爛豪華スピード感ある演出で、足の長い踊手達は皆美しかったが客席に陸軍士官学校生とおぼしい制服姿が大勢居たのには驚かされた。 3日目はいよいよオペラ座の「ジョージ・バランシンの夕べ」であった、胸を踊らせオペラ座の階段をのぼった。座席は姪が粘りに粘りやっと手に入れた自慢の良い席で落ち着いて鑑賞出来たのは幸せであった。プログラムNO1は「コンチェルト・バロック」でパランシンの速い動きに踊手は良くついていき、ごまかしの無い格調高い作品に仕上がっていた、ただ日本とNYでの記憶はたしか黒色の稽古着であったはずが、白色の稽古着に変わって居たのが不思議であった。次はジエローム・ロビンスの「牧神」で、この作品は1953年初演後日本でも上演されたが当時のキャスト、モンシオンとアレグラ・ケントの印象があまり強くロビンスの振付を追う時間になってしまった。ただ新しい発見は、客席と舞台を隔てている見えない鏡の部分の上の所に、一本の銀色のバトンが有った事であった、このバトンは鏡の存在を強調するためと思えるのでかって私が見逃していたのか、また何時から加わったのであるか知りたく思えた。次は、AURELIE DUPONT(オレリー デュポン)、MANUEL LEGRIS(マニエル ルグリ)の「Tchaikovski-pasdudeux」で日本でもしばしば上演される作品でもある。しかし、このテンポ速い音楽と厳しいバレンシンの振付について行く事の出来ない日本人の踊手はしばしば音楽のスピードを落として踊る時がある。私もニューヨーク・シテー・バレエ団の演ずるVTRを持っているが、勿論この速いテンポを楽々と踊りきっている。作品を演ずると云う事は作家の想像力を理解し、作家の理想的条件で表現する事である、自己の技術上の弱点をカバーするために音楽のテンポの変更など論外であり日本のバレエ界も良く考えてほしいものである。幕が開くと実に軽快に踊りは展開して行った、二人の演技は完全を通り越して完璧であった、音楽のテンポは私のVTRより速く感じられかたずを飲んだ、中でもコーダのフェテのラストピルエットを3回転できれいに決めゆっくりと微笑みを見せるなど全てに余裕を持ち観客を湧かせた、勿論多くのアンコールがこれに続いたのはお解り頂けると思う。最後の作品はバランシンの「セレナーデ」が重々しく開幕した、始まりの六番ポジションから一番ポジションに変化するところは「ピ!」と音が聞こえるような鋭ささえ感じるコールド・バレエの存在感は、さすがオペラ座バレエ団のそれもホームグランドでの演技であり荘重に幕を閉じた。この三日間の劇場通いに久方ぶり私は舞踊家としての自覚をおぼえ、次の訪問地ウイーンに向かった。次回はそのウイーンで出合った素晴らしいオペラ「ラ・ポエーム」にふれたいと思う。 |
|||||
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.