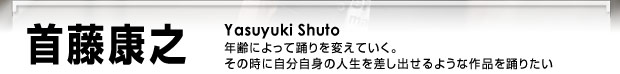神秘的パワーあふれる舞台に思わず吸い込まれ、劇場をあとにする時には心が爽やかさと幸福感に満ちている――首藤康之は私たちにそんな時間をもたらしてくれる数少ないダンサーだ。
鋭い感性と深い視座のもとに、彼が発する豊かな言葉。それはすべての若いダンサーへの贈り物である。
首藤さんは以前、踊ることは舞踊言語の旅をすることだと言ってらした。
先日、テレビではバリ島での踊りを拝見しました。
とても興味があったんです。バリの人たちはダンスを職業とせず、さまざざまな人たちが神に捧げるため、自分のために楽しみながら踊っていて、それが文化、生活になっている。それが自然でシンプルで、皆さん純粋な思いでやっていて、そんなに力が入っていないのにすごい踊りをするんです。
僕の先生は3歳から37年間踊っていますが、ご自分の「バリス」という男の踊りをまだまだだと言ってらした。僕も踊ってみてこの動きはバレエと似ているな、マイムっぽいなとか、すべてがつながっていると感じる瞬間があって、ほんとに舞踊って素晴らしいなと改めて感じました。

首藤さんご自身はバレエ・ダンサーになろうと思ったのはいつですか?
発表会で男の子1人だったんですが、「ジゼル」のペザントのヴァリエーションで舞台に立った時に決まった、という感じでしたね。
小学5年生でしたが、出る前に身体の血液が全部取られてしまったというぐらいに緊張して(笑)。
でも舞台に一歩踏み出して、ライトが当たってお客さんの目がこちらを向いて音楽が鳴ると、その血がどんどん戻ってきてすごく自由になれたんですね。
恐怖がどんどん快感に変わっていくというような、言葉ではうまく言い表せないんですけれども、もう何にも変えられない瞬間だなと思って。
それは今でも同じで、本番前は何かに頼りたいぐらい緊張するんです(笑)。
優れたパフォーマーは皆さんそう言います。でも、いったん舞台に出ると解放される、と。
そういう人でないと観客を感動させられないのでは。その人が解き放たれるのを見て、客席は快感とか一体感とか浄化を味わう。ダンサーが舞台に出る前と後で変わらないことのほうが、不自然なのかもしれません。
そうですね、なんというかわからないけれど、踊っている時、舞台で表現をしている時がやはりほんとの自分というか、お客様が一番僕のことを僕自身よりも知っているような気がしますね。
バレエはご自分から習いたいと?
自分から言いました。きっかけは小学2年生で見たミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」。森重久弥さん主演の舞台でした。大分文化会館は僕にとっては初めての劇場体験で、チケット切ってもらってホワイエから客席に入って、緞帳があって暗くなると、線を引いた一歩先に全く自分の世界とは違う世界が繰り広げられている。なんてことが起こっているんだろう、と。もちろん小2ですからユダヤの話はほとんどわからなかったんですが、不思議な感覚にとらわれて、ここはすごくいいなあと思った。
ある日、小学校の友達の発表会を見に行くと、あのミュージカルと同じ舞台でみんな踊っている。バレエを習えばここで踊れるんだって思ったんです。
ニューヨーク行きもご自分から?
はい。バレエを習って以来、僕は稽古も、劇場っていう空間も大好きになった。今でも劇場は一番落ち着く場所なんですけど、その頃には、毎日稽古があって毎日劇場で見られれたらいいなと思って。
当時は外国といえばアメリカで、福岡のアメリカ領事館に行って情報を得るという時代でした。ニューヨークへは11か12歳の頃に1人で初めて1週間行きました。小さなホテルをとってもらって、今は治安が良くなりましたが当時は怖くて。着いたらいろんな人が話しかけてくるからトランクには名前を書かない。タクシー乗り場に直行して、証明があるのを確認してイエロー・キャブに乗るとか。
いろいろ僕なりに調べて、オープン・クラスも受け、劇場にも行きました。ただ、シーズンじゃなかったのでその時はバレエはほとんど見られなかった。それで毎日タイムズスクエアで並んでチケット買って、ブロードウェイに行ってミュージカルを見ました。
11,2歳の少年が1人で! ご両親もよく送り出してくださいましたね。
そうですね、全部自分でやるなら行ってもいいってことだったんで。その後もコネチカットにあるハートフォード・バレエのサマー・スクールに行ったりしていましたね。
学校では首藤君はバレエをやってる男の子っていうふうに見られていたんですか。
最初は恥ずかしくてやっぱり隠していましたね。あえては言わないようにして。
だけど胸のなかには踊りに対する情熱がフツフツとわいていたわけですね。
もう日に日に増す一方で(笑)、好奇心を抑えることもできず。
東京バレエ団に出てきた時もそうだったんですけど、何かやりたい時には本能的に感じたまま行動してきました。それは今でも変わらないですね。「アポクリフ」を振り付けたシディ・ラルビ・シェルカウイも、琵琶湖ホールで行われていた「ダヴァン」という作品の広告がすごい素敵で、時間があるから行って観たんです。
それはそれは素晴らしいパフォーマンスで、そこから彼とコンタクトをとるようになり、ベルギー王立モネ劇場での初演につながっていきました。いろんなことを知らないと、こうなりたいという思いもわいてこない。子供の頃から芝居やコンサート、映画とか劇場に通っていろいろ見たり感じたりしてきたことが、僕のベースになっているんだと思います。
ところで身体の表現芸術であるバレエには、ある程度の年齢にくるとたとえば古典は踊れなくなるということがありますが、どうお考えですか。
そうですね、古典バレエには踊れないものもありますし、踊る必要もないのかもしれませんね。
僕も、自分自身が踊るレパートリーとこれからやっていきたいダンスというものに少しズレが出てきていたので東京バレエ団を離れました。もちろん1つの踊り「白鳥の湖」をずっと一生踊り続けるという考え方もあってそれはそれで素晴らしいと思う。僕自身はやはり年齢によって踊る作品を変えていきたい。
その時に自分自身の人生を差し出せるような作品を創作し踊りたくなったんです。

中村恩恵さんとはどのように出会われたのですか?
最初、恩恵さんは踊らないけど彼女の振付作品に出てくれませんかと言われたんですね。
その時は僕自身がちょっと作品のキャラクターに合わないと思ったので、お断りしたんです。
あんな断り方したからもう連絡はこないかなと思ったら、その1か月後に神奈川芸術舞踊協会でデュエットをつくる企画があるので一緒に踊っていただけませんかと誘ってくれました。
それで創作を始めたんですけが、初めは2人ともすごくナーバスではあったけど創作の最初の段階から音楽を聞いて、一緒に手を取り合って動く感覚が心地よくてまったく違和感がなかったんですね。
同じ音楽を聞いて同じことを同じ瞬間に考えていることがよくあって。そしてやっぱり素敵なデュエットができました。創作には女性の力は絶対に必要ですが、彼女とだったらそれだけじゃなくジェンダーを越えてもいろんなものをこれからつくり出せるんじゃないかとすごく感じています。
デュエットの「The Well-Tempered」、横浜で拝見しました。これまで違う人生を歩んできたダンサー2人の間に何が生まれるかというスリルがあって、踊りに対するストイックでピュアな姿勢がおふたりとも似ているのを感じました。今度またおふたりで新国立劇場で「ソネット」を踊られるんですね。
はい。今回はシェイクスピアという偉大な劇作家のものなので、あまり抽象的な作品にせずに、具体的で演劇的な作品にしたいなと思いまして。ソネットっていうのは愛の詩ですが、この世の中にはいろんな愛のかたちがあると思うんですよ。母性愛もあれば友愛も兄弟愛、もちろん異性の愛、同性愛、いろんなかたちがある。そういったさまざまな愛のかたちをシェイクスピアの書いた詩で表現できたら、と思っています。
- vol.35 西川箕乃助
- vol.34 伊藤範子
- vol.33 平多実千子
- vol.32 中村祥子
- vol.31 冨田実里
- vol.30 青山季可
- vol.29 内田香
- vol.28 下村由理恵
- vol.27 鈴木稔
- vol.26 森山開次
- vol.25 堀内元・堀内充
- vol.24 酒井はな
- vol.23 平多宏之
- vol.22 森 嘉子
- vol.21 津村禮次郎
- vol.20 首藤康之
- vol.19 金田あゆ子
- vol.18 金森 穣
- vol.17 TAKAHIRO
- vol.16 小島章司
- vol.15 逸見智彦
- vol.14 中村恩恵
- vol.13 舘形比呂一
- vol.12 金井芙三枝
- vol.11 永橋あゆみ
- vol.10 麿 赤兒
- vol.9 レフアとも子
- vol.8 松本晋一×穴田英明
- vol.7 小山久美
- vol.6 小林照子
- vol.5 鍵田真由美×佐藤浩希
- vol.4 平山素子
- vol.3 横井茂×金田和洋
- vol.2 名倉加代子
- vol.1 西島千博